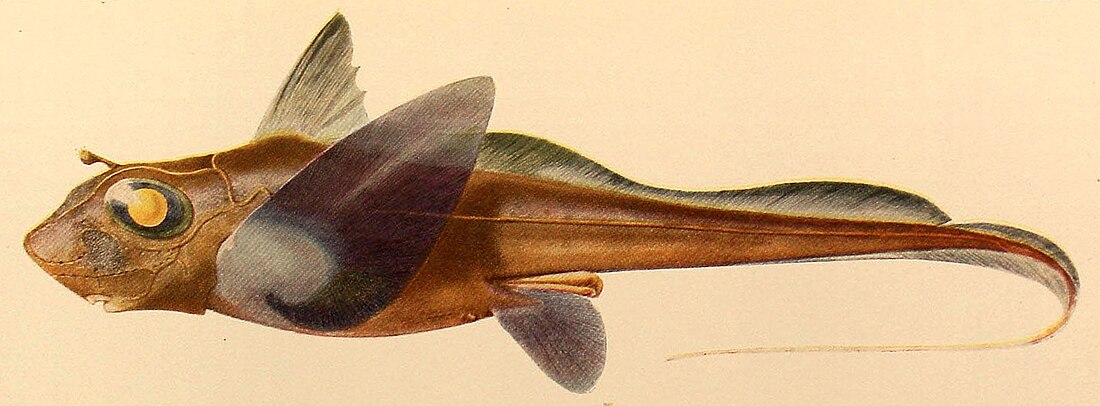トップQs
タイムライン
チャット
視点
ギンザメ目
ウィキペディアから
Remove ads
ギンザメ目 Chimaeriformesは、軟骨魚綱全頭亜綱(ぜんとうあこう)の下位分類群。3科6属に約50種が含まれ、日本近海には11種が生息している。現在は50種ほどの小さな分類群だが、化石記録によると多様で豊富な分類群であったとされる。板鰓亜綱との共通祖先は約4億年前に存在した[2]。現生種は多くが深海に生息する[3]。
Remove ads
形態

頭部は大きく尾は先細りで、体は柔らかいサメのようである。全長は150 cmに達する種もいる。骨格は軟骨で構成される。皮膚は滑らかで、鱗や皮歯は無い。しかし孵化したばかりの稚魚の背中には皮歯の列があり、雄の生殖器は鋸歯状である[4]。鰓弓は鰓蓋に包まれており、胸鰭前部に開口部がある[5]。総排出腔をもつ板鰓類とは異なり、肛門と生殖器の開口部は別々である。
胸鰭を用いて水中を羽ばたくように泳ぐ。胸鰭の後方には小さな腹鰭があり、臀鰭がある属も知られる。ギンザメ科、テングギンザメ科の尾鰭は薄くて鞭状であり、上下が対称的である。ゾウギンザメ科の尾鰭はサメと同様に異尾である。背鰭は2基あり、第一背鰭は大きな三角形で、第二背鰭は小さい。防御のため、背鰭の棘に毒をもつ種もいる[4]。
多くの種では吻に感覚器官があり、獲物の電気信号を感知している[5][6]。口蓋方形軟骨が脳函と融合している。後頭部は椎骨の複合体に支えられており、背鰭棘とも接続している[4]。
歯は6枚の歯板から成り、生涯成長し続ける。下顎の先端に一対、上顎に沿って二対がある。これらの突き出た歯板によって獲物を粉砕する[4]。歯の大部分は象牙質だが、プレロミンというエナメル質のように固い部分がある。プレロミンはシートまたはビーズ状に配置され、骨と同様に間葉由来の組織によって沈着する。またエナメル芽細胞由来の物質によるものでなく、他の動物では歯の中で結晶化する物質により硬化する[7]。
Remove ads
生態
北極海と南極海を除く全世界の温帯海域に分布し、水深2,600 mまでの海底に生息しており、水深200 mより浅い場所ではほとんど見られない。しかしゾウギンザメ、カイブツギンザメ、ミダレボシギンザメは浅い場所でみられることが多く、水族館でもよく飼育される[8]。主に甲殻類、その他にもクモヒトデや軟体動物を捕食する[9]。現生種は底生生物を粉砕して捕食しているが、石炭紀には遊泳性の吸引捕食者も知られていた[10]。雄にはクラスパーがあり、交尾を行う。卵は細長い紡錘形である[1]。また交尾を補助するために特殊な構造を持っている[5][11]。額から棒状の突起を伸ばし、交尾中に雌の胸鰭を掴む。また腹鰭の前の袋の中には鋸歯状の突起があり、交尾中に雄を雌に固定する。クラスパーは軟骨で融合され、先端で分岐して葉状になっている[4]。カイブツギンザメの鰓にはChimaericola leptogaster という単生綱の寄生虫が寄生する。
Remove ads
保全と脅威
一部の種は混獲や乱獲の影響を受けている。IUCNによれば、4種が危急種としてリストされ、さらに4種が近危急種としてリストされ、さらに多くの種がデータ不足とされている。多くの種は生息範囲が限られており、混獲報告は通常正確さが不十分であるため、混獲の実態は不明である。データの欠如により、個体数の減少が見過ごされている種がいる[12]。
沿岸に生息するいくつかの種、例えばゾウギンザメ科、Hydrolagus bemisi、Hydrolagus novaezealandiae などは、肉を目的として漁獲されている。現在の保護計画が制定される前の20世紀には、ゾウギンザメが深刻な乱獲を受けた。Neoharriotta pinnata は肝油を目的としてインド沿岸で標的にされており、最近の捕獲率の低下は個体数の激減を示している可能性がある。Callorhinchus callorynchus、Neoharriotta carri、カイブツギンザメ、ギンザメダマシ、ミダレボシギンザメ、およびHydrolagus melanophasma は生息域の特定の地域で混獲率が10%を超えており、急激に減少している種もいる。サメのように鰭を狙った漁業は行われていない[12]。
もう一つの脅威は、沿岸の産卵場所や深海のサンゴ礁の生息地の破壊である。ゾウギンザメなど沿岸に近い場所に生息する種は、気候変動の影響を受けやすい。強い嵐や海水温の上昇により、孵化を完了するために必要な安定した環境が破壊され、卵の死亡率が増加すると予測されている[12]。
分類
要約
視点
21世紀初頭には、深海探査の発達のため多くの新種が記載された[3]。8%の種が絶滅の危機に瀕している[13]。
ギンザメ亜目 Chimaeroidei Patterson, 1965
ゾウギンザメ科 Callorhinchidae
ゾウギンザメ科 Callorhinchidae は1属3種。全て南半球にのみ分布しており、日本近海では見ることはできない。鉤状の吻をもつ。
- ゾウギンザメ属 Callorhinchus
- Elephant fish Callorhinchus callorynchus (Linnaeus, 1758)
- Cape elephantfish Callorhinchus capensis Dumeril, 1865
- ゾウギンザメ Ghost shark Callorhinchus milii Bory de Saint-Vincent, 1823
ギンザメ科 Chimaeridae
ギンザメ科 Chimaeridae は2属約40種を含む。日本近海にはギンザメなど8種が生息する。ギンザメ科はゾウギンザメ科・テングギンザメ科のような特徴的な構造の吻をもたない。
- ギンザメ属 Chimaera
- Chimaera Chimaera cubana Howell Rivero, 1936
- ジョルダンギンザメ Chimaera jordani Tanaka, 1905
- Bight ghostshark C. lemures (Whitley, 1939)
- Carpenter's chimaera Chimaera lignaria Dider, 2002
- カイブツギンザメ Rabbit fish Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758
- ギンザメダマシ C. ogilbyi (Waite, 1898)
- シロブチギンザメ Chimaera owstoni Tanaka, 1905
- Chimaera panthera Dider, 1998
- ギンザメ Silver chimaera Chimaera phantasma Jordan & Snyder, 1900
- アカギンザメ属 Hydrolagus
- Smalleyed rabbitfish H. affinis (de Brito Capello, 1868)
- African chimaera H. africanus (Gilchrist, 1922)
- イトヒキギンザメ H. alberti Bigelow et Schroeder, 1951
- Hydrolagus alphus
- ココノホシギンザメ H. barbouri (Garman, 1908)
- Pale ghost shark Hydrolagus bemisi
- ミダレボシギンザメ Spotted ratfish H. colliei (Lay & Bennett, 1839)
- Philippine chimaera H. deani (Smith & Radcliffe, 1912)
- ニジギンザメ H. eidolon (Jordan & Hubbs, 1925)
- Hydrolagus lusitanicus
- オオメアカギンザメ Bigeye chimaera Hydrolagus macrophthalmus F. de Buen, 1959
- Striped rabbitfish Hydrolagus matallanasi
- Galapagos Ghost Shark Hydrolagus mccoskeri
- ムナグロギンザメ Large-eyed rabbitfish H. mirabilis (Collett, 1904)
- アカギンザメ Spookfish H. mitsukurii (Jordan & Snyder, 1904)
- Dark ghost shark H. novaezaelandiae (Fowler, 1911)
- ムラサキギンザメ Purple chimaera H. purpurescens (Gilbert, 1905)
- Hydrolagus pallidus
- Pointy-nosed blue chimaera Hydrolagus trolli Didier & Séret, 2002
- Hydrolagus waitei
テングギンザメ科 Rhinochimaeridae
テングギンザメ科 Rhinochimaeridae は3属8種。日本近海にはアズマギンザメ・ヨミノツカイ・クロテングギンザメ・テングギンザメの4種が生息する。著しく伸長した吻をもつ。
- アズマギンザメ属 Harriotta[14][15]
- アズマギンザメ Harriotta chaetirhampha H. chaetirhampha (Tanaka, 1909)
- ヨミノツカイ Narrownose chimaera H. raleighana Goode & Bean, 1895
- Neoharriotta 属
- N. carri Bullis & Carpenter, 1966
- Sicklefin chimaera N. pinnata (Schnakenbeck, 1931)
- N. pumila Dider & Stemann, 1966
- テングギンザメ属 Rhinochimaera
- クロテングギンザメ R. africana Compagno, Stehmann & Ebert, 1990
- ニシテングギンザメ Spearnose chimaera R. atlantica Holt & Byrne, 1909
- テングギンザメ Pacific spookfish R. pacifica (Mitsukuri, 1895)
Remove ads
進化
要約
視点
良質な化石は不足しており、DNA解析によって種分化が研究されている[16]。全頭亜綱は3億8000万年前のデボン紀に板鰓亜綱と分岐したと考えられている。既知の最古の種はロシアの前期石炭紀の地層から発見された Protochimaera であり、ギンザメ亜目と密接に関連している[17]。現生種に起因する最古の化石はヨーロッパの前期ジュラ紀の地層から得られたものだが、後期三畳紀のロシアからはテングギンザメ科に似た、ニュージーランドからはゾウギンザメ科に似た卵殻の化石が発見されている[18]。現生種と異なり、中生代の種は浅い水域に生息していた[19]。
以下の絶滅分類群が知られる。
- †エキノキマエラ Echinochimaera Lund, 1977 アメリカ合衆国、サープコビアン
- †Protochimaera Lebedev & Popov in Lebedev et al., 2021 モスクワ地域、(ビゼーアン–サープコビアン)
- †Squaloraja ヨーロッパ、(ヘッタンギアン–シネムーリアン)
- †Myriacanthoidei Patterson 1965 (後期三畳紀–後期ジュラ紀)
- †Chimaeropsidae
- †Chimaeropsis Zittel 1887 ベルギー、シネムーリアン
- †ミリアカンタス科 Myriacanthidae Woodward 1889
- †Acanthorhina Fraas 1910 ポシドニア頁岩、ドイツ、トアルシアン
- †Agkistracanthus Duffin and Furrer 1981 オーストラリア、イングランド、スイス、(レーティアン–シネムーリアン)
- †Alethodontus Duffin 1983 ドイツ、シネムーリアン
- †Halonodon Duffin 1984 ベルギー、ルクセンブルク、シネムーリアン
- †メトパカンタス Metopacanthus Zittel 1887 ポシドニア頁岩、ドイツ、トアルシアン
- †Oblidens Duffin and Milàn 2017 デンマーク、プリンスバッキアン
- †ミリアカンタス Myriacanthus Agassiz 1837 英国、(レーティアン–シネムーリアン)
- †Recurvacanthus Duffin 1981 英国、シネムーリアン
- †Chimaeropsidae
- Chimaeroidei Patterson 1965
- †Eomanodon Ward and Duffin 1989 英国、プリンスバッキアン
- ゾウギンザメ科 Callorhinchidae Garman, 1901
- †Brachymylus A. S. Woodward 1894 ドイツ、プリンスバッキアン
- †Bathytheristes Duffin 1995 ポシドニア頁岩、ドイツ、トアルシアン
- †Ottangodus Popov, Delsate & Felten, 2019 フランス、バッジョシアン
- †Moskovirhynchus ロシア、後期ジュラ紀
- †Pachymylus 英国、フランス、中期ジュラ紀
- †エダフォドン科 Edaphodontidae
- †イスキオドゥス Ischyodus 世界中、中期ジュラ紀-中新世 (ゾウギンザメ科に分類される場合もある)
- †Elasmodectes ヨーロッパ、ジュラ紀–白亜紀
- †Elasmodus 世界中、白亜紀-古第三期
- †エダフォドン Edaphodon 世界中、白亜紀-新第三期
- †Ptyktoptychion オーストラリア、前期白亜紀
- †Lebediodon ヨーロッパ、白亜紀
- ギンザメ科 Chimaeridae Bonaparte, 1831
- †Canadodus Popov, Johns & Suntok, 2020 カナダ、漸新世
- テングギンザメ科 Rhinochimaeridae Garman, 1901
- †Amylodon ヨーロッパ、後期白亜紀–漸新世
Remove ads
脚注
関連項目
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads