トップQs
タイムライン
チャット
視点
ポンスレの閉形定理
ウィキペディアから
Remove ads
幾何学において、ポンスレの閉形定理(ポンスレのへいけいていり、英: Poncelet's closure theorem, Poncelet's porism)または単にポンスレの定理[1][2]は、二つの円錐曲線にそれぞれ外接、 内接する多角形が1つでも存在すれば、そのような多角形は無数に存在するという定理である[3][4]。1746年、ウィリアム・チャップル が三角形の場合を証明し、1822年、ポンスレが一般の場合を解決した[5][6][7]。
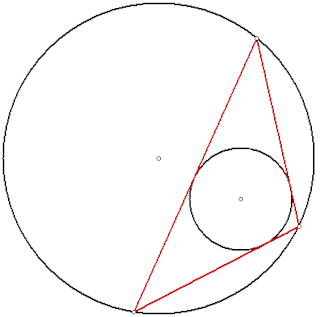
主張
C,Dを二つの円錐曲線とする。3以上の整数nについて、あるn角形がCに外接する(多角形の頂点すべてがC上にある)かつDに内接する(多角形の辺すべてがDと接する)ならば、同様にCに外接しDに内接するn角形を無数に見つけることができる[8]。CまたはD上の任意の点はそのような多角形の接点になり得る。
C,Dがともに円ならばこの多角形は双心多角形と呼ばれる。双心多角形は Poncelet's porism の一部である[9]:p. 94。
証明の概要
C,Dを複素射影平面 P2上の曲線として見る。簡単のため、C, Dは単純な交点を持つとする(非特異で一般の位置にある)。このときベズーの定理よりC, Dの交点は4つ存在する。点cを通るDの接線ℓdの接点をd、(c, d)をもつC × Dの部分代数多様体をXとする。c ∈ C ∩ Dならばdは1つ、でなければ2つ存在する。したがって、射影X → C ≃ P1によりXは、4点以上で分岐した位数2の自己同型で表される。つまりXは楕円曲線である。 (c, d)を同一座標上の点(c, d' )へ移すXの対合をとする。不動点をもつ楕円曲線の対合は、群として、x→p - xと表現されるので、もこの形式となる。同様に射影X → Dも、C, Dの4つの共通接線とDの接点で分岐した位数2の自己同型であり、対合はx→q - xと一致する。したがって合成写像はXへの変換を表す。のべきが不動点を持つならば、そのべきはその不動点で恒等写像である必要がある。C, Dに言い換えると、(対応するdの存在する)ある点c ∈ Cが閉じた軌道をつくる(つまりn角形を作る)ならば、すべての点が不動であるということである。C, Dが退化した場合は極限を取ることで導かれる。
Remove ads
空間への拡張
1880年、フルヴィッツは次のように空間へ一般化した[10][11]。
他に1901, 1904年にフォントネーに論じられ[12][13]、1928年にフランツ・マイヤー(Franz Meyer)に双対を証明された、次のようなものもある[14]。
- 与えられた空間三次曲線に内接し、二次曲面に外接する四面体は、一般に1つ存在し、2つ存在するならば、そのような四面体は無数に存在する。
出典
参考文献
関連項目
外部リンク
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads



