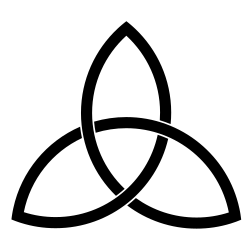トップQs
タイムライン
チャット
視点
桂文治 (初代)
落語家 ウィキペディアから
Remove ads
初代 桂 文治(かつら ぶんじ、安永2年(1773年)(逆算)- 文化12年11月29日(1815年12月29日))は落語家。本名伊丹屋惣兵衛(宗兵衛とも)。息子は同じく落語家2代目桂文治[1]。江戸で「咄の会」が始まり大坂でも人気が伸びたころに現れ、落語を職業とする噺家の始めのひとりである[2]。
Remove ads
来歴・人物
出身については諸説あり、京都の人とも、柴島(現在の大阪市東淀川区)あるいは大和葛城生まれとも伝わる。『摂陽奇観』によれば[要文献特定詳細情報]、京都出身の噺家初代松田彌助の弟子であったという[3]。活動開始期間は寛政6年(1794年)ころからとされ、当時盛んであった素人による座敷での素噺(すばなし)[4][5]に対抗して、鳴物(なりもの)入り、道具入りの芝居噺を創作し、得意としていた。一方、素噺の方も「情深くして実(じつ)あり」と評され、名人であったことが窺える[要出典]。
もともと、玄人(くろうと=プロ)が演じる上方落語は、京都の露乃五郎兵衛[6]、遅れて大坂の米沢彦八[7][8]が大道や社寺の境内において簡素な小屋を掛けて演じていたが、初めて常打(じょううち)の寄席を開いて興行したのは文治で[10]、場所は坐摩神社(いかすりじんじゃ・ざまじんじゃ)境内とされる。上方落語中興の祖[11]であるとともに、寄席の開祖でもある。
現在でも演じられる『蛸芝居』[12]、『昆布巻芝居』[13]、『崇徳院』[14]、『百人一首(千早振る)』[15]、『口合小町』[16]、『反故染』[17]、『滑稽清水(杢の市)』は[18]、文治の作とされる。他にも『尽くしもの』、『女夫喧嘩』と関する一連の噺が得意演目であったという。
多数の門人を擁していたが、特に桂文來、桂文東、桂磯勢(破門となり月亭生瀬と改名[23])、初代桂力造、初代桂文吾の5人が高弟であったという。他に桂北桂舎(「桂文景」から改名)と桂里壽らがおり[要出典]、2代目文治は実子の文吉が継いだ[1]。

1815年巡業先の四日市で死去、享年43(諸説あり[25])。法名釋空海。墓所は同地仏性院にある(泊山霊園仏性院区画)[24][26]。文治が没した三重県に桂文我が住み、2018年時点で初代の墓を守っている[24]。
息子が二代目文治を名乗り[1]、長女・幸は夫の壽遊亭扇松の没後に扇松の弟子で江戸芝金杉出身・扇勇の後妻に入る。江戸へ戻った扇勇は三代目文治を襲名し[1]、以降、東西で文治の名は分かれた[27]。
なお、本名である「惣兵衛」は、上方桂派の系譜で二代目桂ざこばの弟子(三代目桂米朝の孫弟子)である桂そうばが2025年3月に「二代目桂惣兵衛」を襲名の形で名乗り、死没から210年を経て名跡の形で復活する事となった[28]。
Remove ads
主な著作
文治が落語の道に入る少し前に江戸で落語の書籍化が流行し、大坂でも出版が盛んであった[29][30]。
主な著書に『おかしいはなし』(松田彌助と共著)、『桂の花』(桂文公と共著)、『臍の宿かえ』(1812年刊)などがある。
以下、題名の50音順。
脚注
参考文献
関連項目
関連資料
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads