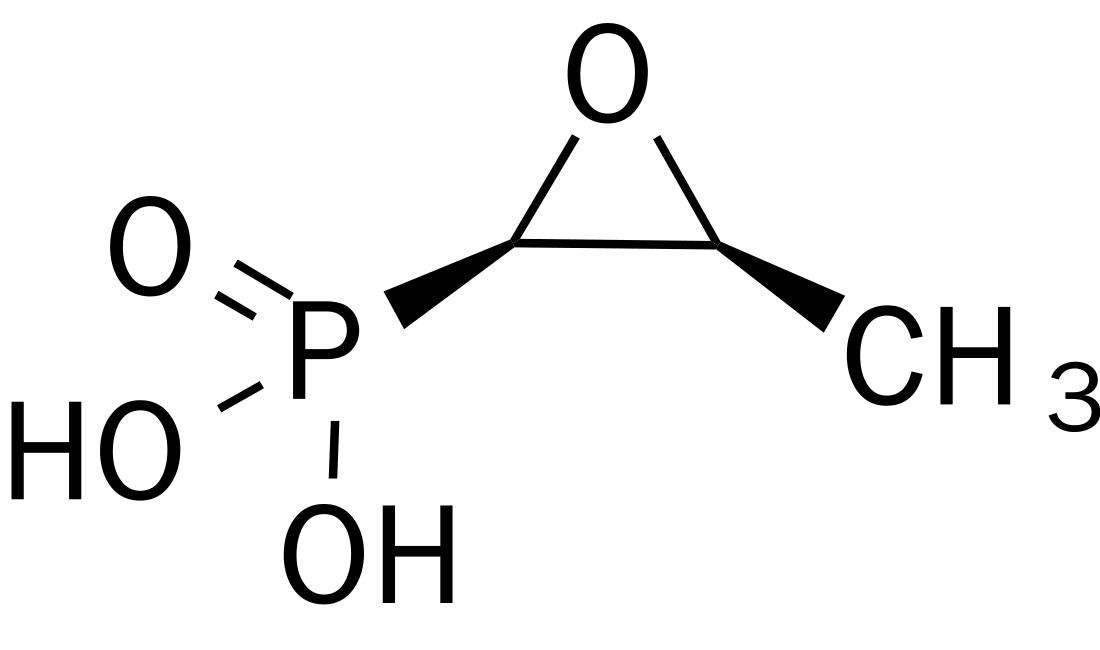トップQs
タイムライン
チャット
視点
ホスホマイシン
ウィキペディアから
Remove ads
ホスホマイシン(Fosfomycyn、Phosphomycin、Phosphonomycin)とは、ストレプトマイセス属の真正細菌が産生する広域スペクトル抗生物質[1]の一つである。商品名ホスミシン。カルシウム塩が経口剤、ナトリウム塩が注射剤と点耳剤として製造されている。構造は単純で類似構造を持つ抗生物質は未だに確認されていない。
Remove ads
禁忌
製剤成分に過敏症の既往を有する患者のほか、低張性脱水症の患者は脱水が増悪する可能性があるので注射剤は禁忌である[2]。
副作用
経口剤の添付文書に記載されている重大な副作用は、血便を伴う重篤な大腸炎(偽膜性大腸炎等)である[3]。注射剤にはそれに加えて、ショック、アナフィラキシー様症状、汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少、肝機能障害、黄疸、痙攣が記載されている[2]。点耳剤に重大な副作用は設定されていない[4]。
効能・効果
- グラム陽性菌:ブドウ球菌属☆※*、
- グラム陰性菌:大腸菌☆※、セラチア属☆※、プロテウス属☆※*、モルガネラ・モルガニー☆※、プロビデンシア・レットゲリ☆※、緑膿菌☆※*、赤痢菌※、サルモネラ属※、カンピロバクター属※
が原因である敗血症☆、急性気管支炎☆、肺炎☆、肺膿瘍☆、膿胸☆、慢性呼吸器病変の二次感染☆、膀胱炎☆※、腎盂腎炎☆※、感染性腸炎※、腹膜炎☆、バルトリン腺炎☆、子宮内感染☆、子宮付属器炎☆、子宮旁結合織炎☆、深在性皮膚感染症※、涙嚢炎※、麦粒腫※、瞼板腺炎※、中耳炎※*、外耳炎*、副鼻腔炎※
☆:注射剤に記載、※:経口剤に記載、*:点耳剤に記載
ホスホマイシンは各種の尿路感染症に短期間大量投与される。単回経口多量投与の報告もある[5]。 トブラマイシンとの合剤が嚢胞性線維症患者の肺感染症治療に応用された[6][7]。
静脈内投与されるホスホマイシンは、多剤耐性菌による感染症の治療において、その使用が増加してる。これは、他の抗菌薬との相乗効果を活かし、耐性の発生を防ぐために併用薬として使用されることが多い為である。実臨床の場では、ホスホマイシンは主に肺炎(34%)、菌血症(22%)、および尿路感染症(21%)の治療に使用されている。大多数のケースではβ-ラクタム系抗菌薬との併用が行われており、約半数の症例では経験的治療として用いられている。成人の1日投与量は通常12〜24グラムの範囲である。持続点滴投与を行う場合は、初回投与として8グラムを投与した後、1日16グラムまたは24グラムを投与する。持続点滴投与は腎機能が正常な患者に推奨される。[8]。
ホスホマイシンの忍容性は高く、副作用は少ないとされる[5]が、治療中の耐性の出現率が高く、重症感染症の治療継続ができない場合が多い。小児ならびに75歳以上の高齢者には推奨されない[9]。
さらなる使用方法が提案されている[10]。 世界的な耐性菌出現が近年問題視されている[11]。
動物用医薬品としては、牛の大腸菌性下痢症及びサルモネラ症に使用され、飼料添加物としても使用されている。また、すずき目魚類の類結節症及びエドワジェラ症に対して飼料添加物として使用される。
作用機序
ホスホマイシンはMurAと呼ばれるUDP-N-アセチルグルコサミンエノールピルビン酸トランスフェラーゼ酵素を失活させる事で殺菌的に作用する[12]。MurAはペプチドグリカンの生合成過程の内、ホスホエノールピルビン酸(PEP)をUDP-N-アセチルグルコサミンの3'位の水酸基へ移動させる役割を持っており、このピルビン酸基はペプチドグリカンのペプチド部分とグリカン部分を繋ぐ役目を果たす。ホスホマイシンはPEPの代わりにMurAに結合し、その活性部位であるシステイン残基(Escherichia coli の場合は115番)をアルキル化して作用を封じる[13]。この様にホスホマイシンは、細菌の細胞壁のペプチドグリカン合成を阻害することにより抗菌力を発揮する。βラクタム系の様に細胞壁のムレイン架橋を阻害するのではなく、ムレイン単体生合成を阻害することが特徴である。ムレイン単体合成阻害薬には他にバンコマイシンがある。
ホスホマイシンはバクテリア体内へグリセロールリン酸輸送体にて取り込まれる[14]。
Remove ads
抗菌スペクトルと感性
ホスホマイシンの抗菌活性はグラム陽性菌とグラム陰性菌の両方に対して有効であり、E. faecalis、E. coli、シトロバクター属、プロテウス属等のグラム陰性菌を殺菌できる。低pH環境下ではより活性が強く、尿中に未変化の活性体が排泄されるので尿路病原菌起因性の予防・治療に適している。 注目すべき点は、S. saprophyticus、クレブシエラ属、エンテロバクター属に対する活性一定ではないので、最小発育阻止濃度(MIC)を確認した上で用いるべきである点であろう。他の抗生物質と交差耐性を持たないので、基質特異性拡張型βラクタマーゼ(ESBL)を産生する病原体に対する活性は、特にESBL産生型E. coli において良好または著効である。 ホスホマイシンに感性の起因菌による単純性尿路感染症に対する臨床データがある。しかし、感性の判断基準である64mg/Lは全身性感染症については適用すべきでない。欧州抗菌薬感受性試験委員会(EUCAST)は、感性の基準として32mg/Lを採用している[15]。
Remove ads
急性毒性
耐性
非必須なグリセロールリン酸輸送体の不活性化によってホスホマイシン耐性が出現する[16][17]。
ホスホマイシン耐性酵素
ホスホマイシンの耐性に寄与する酵素群の遺伝子が、染色体とプラスミドの両方から見付かっている[18]。
ホスホマイシン耐性に関する3つの遺伝子(FosA、FosB、FosX)はグリオキシラーゼに分類される酵素をコードする。これらの酵素はホスホマイシンの1位の炭素に求核反応してエポキシ環を開き、ホスホマイシンを不活化させる。求核反応に用いる基質に応じてFosA(グルタチオン)、FosB(バシリチオール[19][20])、FosX(水(H2O)[18])に分類されている。一般にFosAおよびFosXはグラム陰性菌が、FosBはグラム陽性菌が産生する[18]。
FosCはホスホマイシンにATPのリン酸基を転移させる酵素であり、この反応によってもホスホマイシンは不活化される[21]。
Remove ads
生合成遺伝子群
Streptomyces fradiae が持つホスホマイシンを生合成する遺伝子群を全てStreptomyces lividans に移植する試みが2006年に成功した[22]。
開発の経緯
ホスホマイシンは最初、土壌サンプルの培養液中に含まれていたStreptomyces fradiaeから、発育中のバクテリアをスフェロプラスト化させた事から発見され、1969年に出版された論文集の中で報告された[23]。1971年に工業的に生産される様になった[24]。
出典
外部リンク
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads