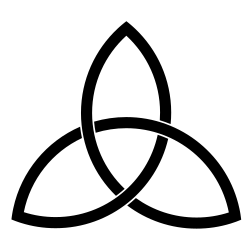トップQs
タイムライン
チャット
視点
桂文屋
ウィキペディアから
Remove ads
桂 文屋(かつら ぶんや、慶応3年12月(1867年12月もしくは1868年1月[注釈 1] - 1909年(明治42年)3月16日[1]。、明治時代の上方落語の落語家(上方噺家)。本名:
この項目は著作権侵害が指摘され、現在審議中です。 審議の結果、該当する投稿以降の全ての版またはこのページ全体(すべての版)が削除される可能性があります。問題箇所の適切な差し戻しが行われていれば、削除の範囲は問題版から差し戻し直前の版までとなる可能性もあります。適切な差し戻しが行われていないと考えられる場合は、この版の編集や引用はしないでください。著作権上問題のない自分の投稿内容が削除される可能性のある方は、早めに控えを取っておいてください(詳しくはこちらの解説をお読みください)。 該当する投稿をされた方へ: ウィキペディアでは、著作権上問題のない投稿のみを受け付けることになっています。他人の著作物を使うときをお読み頂いた上で、審議にご協力をお願いします。自分の著作物を投稿されていた場合は削除依頼を出されたらをご覧ください。 審議が終わるまで、このお知らせを除去しないでください。 (以下、著作権侵害の可能性がある箇所を取り除いた内容を暫定的に表示します。) |
軽口の笑福亭松右衛門の実子[1]。本名の
幼少時から本名(一時笑福亭だら助)[要出典]のままで寄席に出ており、2代目笑福亭松鶴の門下だったという[1]。次に3代目桂文吾の門下で金吾となり、最後に2代目桂文枝の門下で文屋となった[1]。
本職の落語の腕前は「下手」と評されながらも、文人の食満南北や渡辺霞亭からその人柄を愛された[1]。3代目桂米朝によると、食満南北は一時期文屋の家に仮寓した(道楽が過ぎて家にいられなくなったため)という[3]。
音曲では一中節、胡弓に琴を手がけたほか、陶芸(楽焼)に茶道、絵画に俳句と、多芸多趣味の人であった[1]。陶芸では両方に口のある土瓶を作ったが、引き取り手がなかったとされ、死去から3か月後にそれを記念する碑が大阪市天王寺区の壽法寺に建立されている[1]。同寺には文屋の墓もある[3]。
死去から約半年後に『大阪朝日新聞』の「珍物画伝」に生前の奇行が紹介された[1]。それによると、家財が仏壇しかなく、襖に破産した銀行の株券を貼りつめ、夜にも照明を付けず、就寝時は水を詰めた一升の徳利を天井からつるしていた(泥棒がぶつかれば水がこぼれて自分の目が覚めるという仕掛け)[1]。生涯独身であった[1]。
新作も多く手がけ、『いらち俥』(東京では『反対俥』)『阿弥陀池』(発表当時は『新作和光寺』)『染色』の作者とされる[1]。
辞世の句は「夢さめて酒まださめず春の月」[1]。
Remove ads
脚注
参考文献
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads