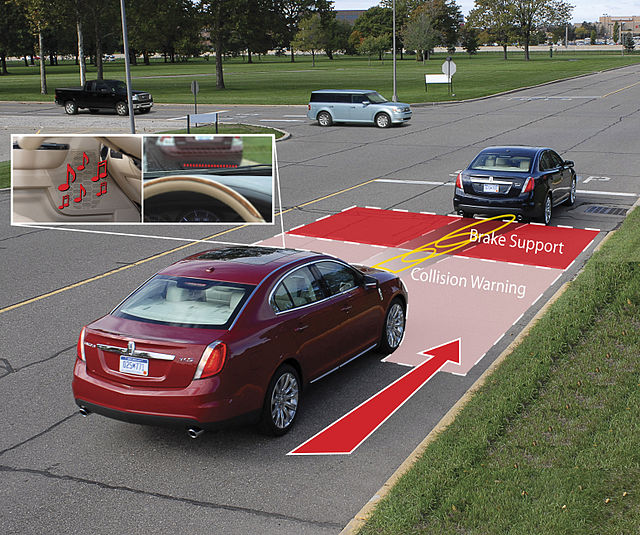| 名称 |
センサ |
主な搭載車種 |
解説 |
| トヨタ自動車(レクサス) |
| プリクラッシュセーフティシステム |
ミリ波レーダー |
エスティマ(3代目・3期型まで)
プリウス(3代目)
SAI
プリウスα(前期型) |
2003年2月以降から搭載。最初期は警報とブレーキアシストのみで、自律的にブレーキ操作は行われないものだったが、2003年8月より運転者のブレーキ操作がない場合に自律的にブレーキをかけ、減速による衝突被害軽減も行うタイプへ変更される[58]。ただし、自動停止による衝突回避はせず、減速による被害軽減までに留めている(自動停止が行われなかった経緯は自動停止参照)。
ミリ波レーダーのみの型は歩行者検知を行わないが、カメラ・レーダーの複合型は歩行者検知も行う。 |
| ミリ波レーダーとカメラ |
クラウンマジェスタ(5代目)
ハイラックス(8代目・日本仕様) |
| プリクラッシュセーフティシステム |
ミリ波レーダー |
クラウン(14代目)
ハリアー(3代目)
クラウンマジェスタ(6代目)
カムリ(9代目・後期型)
プリウスα(後期型)
アルファード(3代目)
ヴェルファイア(3代目)
レクサス・IS(3代目・前期型) |
2012年12月以降から搭載。衝突が避けられないと判断したときは相対速度15km/h以上で自律的にブレーキが作動し、最大30km/h程度減速して衝突を回避あるいは衝突の被害を軽減する。
従前のシステム(上述)と同名であるが、このタイプより15km/h〜30km/h程度で自動停止による衝突回避も可能となった[59][60]。歩行者の検知は行わない。
これにより、IIHSの評価においても旧プリクラッシュのプリウスαは「Doesn't Meet Minimum Criteria(最低基準未満)」と低い評価なのに対して[61]、本システムのプリウスαは「6点満点中3点、Advanced(アドバンスド)評価」と評価を高めた[62]。JNCAPによる安全評価が行われたのはこの型からとなっている[63]。 |
| プリクラッシュセーフティシステム |
ミリ波レーダーと画像センサー |
ダイナ(8代目・2016年4月一部改良モデル以降)
トヨエース(8代目・2016年4月一部改良モデル以降) |
日野が開発・製造を担当するダイナ・トヨエース(=デュトロ)のLPG車を除く全車型に搭載。下記日野の項目を参照。 |
| 衝突回避支援型プリクラッシュセーフティシステム |
ミリ波レーダーとステレオカメラ |
レクサス・LS(4代目) |
2006年9月から設定。世界で初のステレオカメラ方式によるシステムを採用し、相対速度40km/h以下で自律的なブレーキにより衝突回避を支援する。相対速度が40km/hを超える状況でも自動で制動を行い、歩行者検知も行う。
価格面で非常に高価なため、2023年現在までLS以外には展開されていない。なお、4代目LSに搭載のものは、Toyota Safety Sense登場以前のJNCAP予防安全性能アセスメントでトヨタ車唯一の40点満点を取得した。 |
| Lexus Safety System +A |
レクサス・LS(5代目) |
プリクラッシュセーフティシステム
(Toyota Safety Sense C) |
赤外線レーザーとカメラ |
当該項参照 |
2015年3月以降から搭載。トヨタは新型のプリクラッシュを含む安全運転支援システムを「Toyota Safety Sense」として設定し、「C」はコンパクトカー向けのシステムとなる。後述の「P」と合わせ、2017年までに日本、北米、欧州のほぼ全てのトヨタの乗用車への設定が予定されている[64]。
10〜80km/hで自律的にブレーキが作動し、衝突を回避あるいは衝突の被害を軽減する。歩行者の検知は行わない。 |
プリクラッシュセーフティシステム
(Toyota Safety Sense) |
2018年4月以降から搭載。上述の「-C」に昼間時の歩行者検知機能を追加したもの。 |
プリクラッシュセーフティシステム
(Toyota Safety Sense P) |
ミリ波レーダーとカメラ |
当該項参照 |
2015年8月以降から搭載。先行してラインナップされた上述の「C」に続く、ミディアム・上級車種・次世代車種向けのシステム。システム構成が異なるため「C」とは一分機能が異なる。
車両に対しては10km/h〜、歩行者に対しては10〜80km/hで自律的にブレーキが作動し、衝突を回避あるいは衝突の被害を軽減する。 |
プリクラッシュセーフティシステム
(Toyota Safety Sense) |
2018年1月以降から搭載。上述の「-P」に夜間時の歩行者および自転車運転者の検知機能を追加したもの。 |
歩行者検知機能付衝突回避支援型プリクラッシュセーフティシステム
(Lexus Safety System +) |
ミリ波レーダーとカメラ |
当該項参照 |
2015年8月より搭載を開始。2017年までに日本、北米、欧州のほぼ全てのレクサス全車への設定が予定されている[65]。
性能的には上述の「Toyota Safety Sense(P)」と同様で、車両に対しては10km/h〜、歩行者に対しては10〜80km/hで自律的にブレーキが作動し、衝突を回避あるいは衝突の被害を軽減する。 |
| スマートアシスト |
赤外線レーザー |
当該項参照 |
ダイハツからOEMを受ける車種(一部グレード)に搭載。下記ダイハツの項目を参照。 |
| スマートアシストII |
赤外線レーザーとカメラ |
当該項参照 |
ダイハツからOEMを受ける車種(一部グレード)に搭載。下記ダイハツの項目を参照。 |
| スマートアシストIII |
ステレオカメラ |
当該項参照 |
ダイハツからOEMを受ける車種(一部グレード)に搭載。下記ダイハツの項目を参照。 |
スマートアシスト
(次世代) |
ステレオカメラ |
当該項参照 |
ダイハツからOEMを受ける車種に搭載。下記ダイハツの項目を参照。 |
| EyeSight(アイサイト) |
ステレオカメラ |
GR86(ZN8型のAT車のみ、2021年~) |
SUBARUからOEMを受ける車種に搭載。下記SUBARUの項目を参照。バージョン表記の無い特殊仕様。 |
| ダイハツ工業 |
| プリクラッシュセーフティシステム |
レーザーレーダーとカメラ |
ムーヴカスタム(4代目・L175S
5代目・LA100S(前期)にメーカーオプション |
|
| スマートアシスト |
赤外線レーザー |
当該項参照 |
4〜30km/h以内の速度で走行中、衝突の危険性を検知するとまず音と表示による警報を行い、それでも衝突の危険がある場合は自律的にブレーキを作動させる。 |
| スマートアシストII |
赤外線レーザーとカメラ |
当該項参照 |
スマートアシストに単眼カメラを追加した機能強化版。 |
| スマートアシストIII |
ステレオカメラ |
当該項参照 |
スマートアシストIIをリニューアルし、ステレオカメラを採用したモデル。 |
| スマートアシストIIIt |
ステレオカメラ |
ハイゼットトラック(10代目・2018年5月一部改良以降) |
スマートアシストIIIを軽トラックの車両特性に合わせて、作動速度域を変更したモデル。 |
スマートアシスト
(次世代) |
ステレオカメラ |
当該項参照 |
スマートアシストIIIに車線逸脱抑制制御機能、アダプティブドライビングビーム、ブレーキ制御付誤発信抑制機能(前方・後方)などの機能を追加したモデル。 |
| 日産自動車 |
| インテリジェントブレーキアシスト |
レーザーレーダーセンサー |
シーマ(5代目)
エルグランド(3代目)
スカイライン(12代目) |
ドライバーが回避操作を行わない場合には緊急ブレーキを作動して、減速して被害を軽減する。自律的に停止まで減速して衝突の回避までは行わない。 |
エマージェンシーブレーキ
(ミリ波レーダー) |
ミリ波レーダー |
スカイライン(13代目・前期型~2019年7月ビッグマイナーチェンジ以降のターボ車のみ)
フーガ(2代目・2015年2月マイナーチェンジ以降)
NV350キャラバン(2016年1月一部改良以降) |
緊急ブレーキを作動して、60km/h以下で衝突を回避、または被害を軽減、60km/h以上で減速して被害を軽減する。歩行者には基本的に作動しない。 |
エマージェンシーブレーキ
(カメラ) |
マルチセンシングフロントカメラ |
エクストレイル(3代目)
セレナ(4代目・2013年12月マイナーチェンジ以降、5代目)
ノート(2代目・2013年12月マイナーチェンジ以降)
リーフ(初代・2015年11月マイナーチェンジ以降)
ティアナ(3代目・2015年2月一部改良以降)
ジューク(2015年11月一部改良以降)
NV150 AD(4代目・2016年11月マイナーチェンジ以降)
デイズ(後期型・2018年5月一部改良モデル以降)
デイズルークス(2代目・後期型、2018年5月一部改良モデル以降) |
フロントカメラを用いたマルチセンシングシステム。[66]
10〜80km/hの範囲で緊急ブレーキが作動し、30km/h以下で衝突を回避または被害を軽減、30km/h以上で減速して被害を軽減する。
停止している車両および歩行者に対しては10〜60km/hで作動する。
車速約60km/h以上では、歩行者に対しては作動しない。 |
インテリジェントエマージェンシーブレーキ
(カメラ+ミリ波レーダー) |
ミリ波レーダーとカメラ |
エクストレイル(3代目・後期型、2020年1月一部改良モデル以降)
セレナ(5代目、2020年8月一部改良モデル以降)
デイズ(2代目、2020年8月一部改良モデル以降)
ルークス(3代目) |
5〜80km/hの範囲で緊急ブレーキが作動し、30km/h以下で衝突を回避または被害を軽減、30km/h以上で減速して被害を軽減する。
歩行者に対しては10〜60km/hで作動する。 |
| ミリ波レーダーと三眼カメラ |
スカイライン(13代目・2019年7月ビッグマイナーチェンジ以降のハイブリッド車のみ) |
エマージェンシーブレーキ
(レーザーレーダー) |
赤外線レーザー |
デイズ(Vセレクション+SafetyII、2015年10月マイナーチェンジ以降~後期型・2018年5月一部改良モデル以前)
デイズルークス(Vセレクション+SafetyII、2015年4月一部改良モデル以降~後期型・2018年5月一部改良モデル以前) |
三菱・eKシリーズの姉妹車であるデイズ(=eKワゴン)、デイズルークス(=eKスペース)の特別仕様車「Vセレクション+SafetyII」に搭載。後に標準装備された。下記三菱自動車の項目を参照。 |
NV100クリッパーリオ(3代目・2019年7月一部改良モデル以前)
NV100クリッパー(3代目・2019年7月一部改良モデル以前) |
スズキからOEMを受けるNV100クリッパーリオ(=エブリイワゴン)に標準装備。NV100クリッパー(=エブリイ)は一部グレードに搭載。下記スズキの「レーダーブレーキサポート」を参照。 |
インテリジェントエマージェンシーブレーキ
(ステレオカメラ) |
ステレオカメラ |
NV100クリッパーリオ(3代目・2019年7月一部改良モデル以降)
NV100クリッパー(3代目・2019年7月一部改良モデル以降)
NT100クリッパー(2代目・2019年9月一部改良モデル以降) |
スズキからOEMを受けるNV100クリッパーリオ(=エブリイワゴン)に標準装備。NV100クリッパー(=エブリイ)、NT100クリッパー(=キャリイ)は一部グレードに搭載。下記スズキの「デュアルカメラブレーキサポート」を参照。 |
| アトラス ディーゼル/アトラス 1.5tクラス(4代目) |
いすゞからOEMを受けるアトラス 1.5tクラス(=エルフ1.5t積)に搭載。下記いすゞ自動車の項目を参照。
フルスーパーロー(=エルフ1.5t積フルフラットロー)は当初搭載されていなかったが、2021年4月一部改良モデルから標準装備。
2021年3月モデルまではエルフ1.5t積とは異なりオプションで装備レス化も可能であった。 |
| アトラス 2tクラス(6代目) |
いすゞからOEMを受けるアトラス 2tクラス(=エルフ2t~3.5t積)に搭載。下記いすゞ自動車の項目を参照。 |
インテリジェントエマージェンシーブレーキ
(ミリ波レーダー) |
ミリ波レーダー |
NV350キャラバン(2016年1月マイナーチェンジ以降) |
設定当初は一部グレードにメーカーオプションであったが、後に全車標準装備された。オプションで装備レス化も可能。 |
| NT450アトラス(5代目・2019年7月マイナーチェンジ以降) |
三菱ふそうトラック・バスからOEMを受けるNT450アトラス(=キャンター)に搭載。下記三菱ふそうトラック・バスの項目を参照。 |
| 本田技研工業 |
CMBS
(追突軽減ブレーキ) |
ミリ波レーダー |
当該項参照 |
2003年から搭載を開始。自律的にブレーキをかけ、衝突による衝撃・被害を軽減する。自動停止による衝突回避までは行わない。 |
CMBS
(衝突軽減ブレーキ) |
ミリ波レーダー |
当該項参照 |
2013年から搭載を開始。本モデルからは低速での自動停止が付加され、衝突回避も可能となった(今まで自動停止が行われなかった経緯は自動停止参照)[67]。
約5km/h以上で作動し、衝突の危険がある場合に警告、緊急時には自律的に強いブレーキをかけて衝突回避・被害軽減を図る。車種によっては単眼カメラを備えたHiDSとして提供されるが、後述のHonda SENSINGと異なり、歩行者への対応は基本的に行わない。 |
CMBS
(Honda SENSING) |
ミリ波レーダーとカメラ |
当該項参照 |
2015年より新型のCMBSを含む安全運転支援システムを「Honda SENSING(ホンダ センシング)」として搭載開始。
約5km/h以上で作動し、車両や歩行者を検知し、衝突の危険がある場合に警告をする。
緊急時には自律的に強いブレーキをかけて衝突回避・被害軽減を図る。
Honda SENSINGに含まれる機能は車種によって違いがあるが、CMBSは全車種同等となっている[68]。 |
| シティブレーキアクティブシステム |
赤外線レーザー |
フィット(3代目・2017年6月マイナーチェンジ以前)
N-WGN
N-BOX(初代・2013年12月マイナーチェンジ以降)
N-ONE(2014年5月マイナーチェンジ以降)
S660
ヴェゼル(2016年2月一部改良以前)
グレイス(2017年7月マイナーチェンジ以前)
シャトル(2017年9月一部改良以前)
CR-Z(2015年8月マイナーチェンジ以降) |
5〜30km/hで走行中、衝突の危険がある場合に警告、緊急時には自律的に強いブレーキをかけて衝突回避・被害軽減を図る。 |
| スズキ |
| プリクラッシュセーフティシステム (PRECRS) |
ミリ波レーダー |
キザシ
エスクード(3代目・2008年から3.2XSに設定) |
自律的なブレーキにより、衝突速度を低減し、ダメージを軽減する。 |
| レーダーブレーキサポート |
赤外線レーダー |
ワゴンR(5代目・前期型(レーダーブレーキサポート装着車))
スペーシア(初代・前期型)
ハスラー
アルト(8代目・2018年12月一部改良以前)
アルトラパン(3代目・2019年6月一部改良以前)
エブリイ(6代目・2019年6月一部改良以前)
エブリイワゴン(3代目・2019年6月一部改良以前) |
5〜30km/hで走行中、衝突の危険性が高いとき、自律的にブレーキが作動し、追突などの危険を回避または衝突の被害を軽減する。 |
| レーダーブレーキサポートII |
ミリ波レーダー |
ソリオ(3代目(レーダーブレーキサポートII装着車))
エスクード(4代目・2018年12月一部改良以前)
バレーノ |
5〜100km/hの範囲、停止している車両に対しては5〜80km/hの範囲で、前方に車があるときにブザーとメーター内ディスプレイでブレーキ動作を促す。
また、衝突の可能性が高い時に緊急ブレーキを行うとブレーキアシストにより衝突速度を減速する。5〜30km/hで走行中の時は自律的にブレーキが作動し、追突などの危険を回避または衝突の被害を軽減する。 |
| デュアルカメラブレーキサポート |
ステレオカメラ |
スペーシア(初代・後期型、2代目・2020年8月一部改良モデル以降)
ソリオ(4代目(デュアルカメラブレーキサポート装着車))
ハスラー(2015年12月一部改良モデル以降)
イグニス(セーフティーパッケージ装着車)
エブリイ(6代目・2019年6月一部改良以降)
エブリイワゴン(3代目・2019年6月一部改良以降)
キャリイ(11代目・2019年9月一部改良以降) |
5〜100km/hの範囲で、前方に車があるときにブザーとメーター内ディスプレイでブレーキ動作を促す。
また、衝突の可能性が高い時に緊急ブレーキを行うとブレーキアシストにより衝突速度を減速する。5〜50km/h未満(歩行者の場合は5〜30km/h未満)で走行中の時は自律的にブレーキが作動し、追突などの危険を回避または衝突の被害を軽減する。
2018年7月発表のソリオ(4代目・後期型)からはステレオカメラが新型になり、夜間の歩行者も検知できるようになった。
ハスラーは初代一部改良モデルの一部グレードのみ搭載。2代目は「HYBRID G スズキ セーフティ サポート非装着車」以外標準設定。 |
| デュアルセンサーブレーキサポート |
赤外線レーダーとカメラ |
アルト(8代目・2018年12月一部改良モデル以降)
アルトラパン(3代目・2019年6月一部改良モデル以降)
エスクード(4代目・2018年12月一部改良以降)
クロスビー
スイフト(4代目(セーフティーパッケージ装着車))
ジムニー(4代目)
スペーシア(2代目・2020年8月一部改良モデル以前)
ワゴンR(6代目(セーフティーパッケージ装着車))
ワゴンRスマイル |
15〜100km/hの範囲(歩行者に対しては15〜60km/hの範囲)で、前方に車または歩行者があるときにブザーとメーター内ディスプレイでブレーキ動作を促す。
また、衝突の可能性が高い時に緊急ブレーキを行うとブレーキアシストにより衝突速度を減速する。5〜100km/h(歩行者に対しては5〜100km/h)で走行中の時は被害軽減ブレーキが作動し、追突などの危険を回避または衝突の被害を軽減する。 |
| SUBARU |
| EyeSight(アイサイト)Ver.1 |
ステレオカメラ |
レガシィ(BL/BP系F型・2008年~)初採用
エクシーガ(YA型B型以降・2009年~) |
前車・歩行者・障害物との衝突リスクが高まると自律的にブレーキをかけ、衝突による衝撃・被害を軽減する。
自動停止による衝突回避までは行わない[69]。(動作範囲 自車速度 2~140 km/h) |
| EyeSight(ver.2) |
レガシィ(BM/BR系B型・2010年~)初採用
当該項(#過去に搭載できた車種)参照 |
前方車両との速度差が約30 km/h以下(理想的状況下) では、自律的ブレーキで衝突回避を図る。
回避限界速度を超える場合は、自律的ブレーキで被害軽減を試みる。(動作範囲 自車速度 1~140 km/h)[70] |
| EyeSight(ver.3) |
レヴォーグ (VM系 2014年~)初採用
当該項(#搭載可能車種)参照 |
前方車両との速度差が約50 km/h以下(理想的状況下、対歩行者の場合は約35 km/h以下)では、自律的ブレーキで衝突回避を図る。
回避限界速度を超える場合は、自律的ブレーキで被害軽減を試みる。(動作範囲 自車速度 1~160 km/h)[71]
自律的ブレーキによる停止後は一部車種を除き、電動パーキングブレーキにより停止状態を保持する。 |
(新世代)アイサイト
(2021年現在) |
ステレオカメラ (前方)とミリ波レーダー(前側方) |
レヴォーグ(VN系・2020年~)初採用
フォレスター(SK系D型・2021年~)
レガシィアウトバック(BT系・2021年~)
WRX S4(VB系・2021年~) |
制御対象物との速度差が約60 km/h以下(理想的状況下)では、自律的ブレーキ(状況に応じて自律的ステアリング操作も併用)で衝突回避を図る。回避限界速度を超える場合は被害軽減を試みる。(動作範囲 自車速度 1~160 km/h)[72]
自律的ブレーキによる停止後は、電動パーキングブレーキにより停止状態を保持する。 |
| トマールレーダー (正式名スマートアシスト) |
赤外線レーザー |
当該項参照 |
ダイハツからOEMを受ける車種(一部グレード)に搭載。上記ダイハツの項目を参照。 |
| スマートアシストII |
赤外線レーザーとカメラ |
| スマートアシストIII・IIIt |
ステレオカメラ |
| スマートアシスト(次世代) |
| マツダ |
スマート・シティ・ブレーキ・サポート
(SCBS) |
赤外線レーザー |
CX-5(初代)
アテンザ(3代目)
アクセラ(3代目)
デミオ(4代目・2017年11月一部改良以前)
CX-3(2016年10月一部改良以前) |
4〜30km/hで走行中、自律的にブレーキをかけて衝突回避をサポート、もしくは衝突による被害の低減を図る。 |
アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート
(アドバンストSCBS) |
カメラ |
アクセラ(3代目・後期型)
アテンザ/MAZDA6(3代目・中期型(2016年8月一部改良以降))
MAZDA3(初代)
デミオ/MAZDA2(4代目(2017年11月一部改良以降))
CX-3(2016年10月一部改良以降)
CX-30
CX-5(2代目)
CX-8
ロードスター(4代目・2018年6月一部改良以降) |
4〜80km/h未満(歩行者の場合は10〜80km/h未満)で走行中、自律的にブレーキをかけて衝突回避をサポート、もしくは衝突による被害の低減を図る。 |
スマート・ブレーキ・サポート
(SBS) |
ミリ波レーダー |
アテンザ(3代目)
アクセラ(3代目・前期型(2014年8月一部改良以降))
MAZDA3(初代)
デミオ(4代目(2016年10月一部改良以降))
CX-3
CX-30
CX-5(初代・後期型(2014年11月一部改良以降))
CX-8 |
15km/h以上で、自律的にブレーキをかけて衝突による被害の低減を図る。
アテンザではSCBS、SBS等の先進安全技術をまとめて「i-ACTIVSENSE」と呼んでおり、SCBSと組み合わせて4〜30km/hで衝突の回避・衝突被害の軽減、30km/h以上では減速して衝突被害の軽減が可能となり[73]、
2016年7月発表のアテンザ(3代目・後期型)以降の一部発売車種は、カメラ(アドバンストSCBS)とミリ波レーダー(SBS)を併用することにより機能・性能が向上した。 |
| エマージェンシーブレーキ |
カメラ |
ファミリアバン(9代目・後期型(2017年2月一部改良モデル)) |
日産からOEMを受けるファミリアバン(=日産・AD)に標準装備。上記日産の項目を参照。 |
| プリクラッシュセーフティシステム |
赤外線レーザーとカメラ |
ファミリアバン(10代目) |
トヨタからOEMを受けるファミリアバン(=プロボックス・サクシード)に標準装備。上記トヨタ「Toyota Safety Sense」の項目を参照。 |
| ミリ波レーダーとカメラ |
ボンゴブローニイバン(3代目) |
トヨタからOEMを受けるボンゴブローニイバン(=ハイエースバン・レジアスエースバン)に標準装備。上記トヨタ「Toyota Safety Sense」の項目を参照。 |
スマートアシスト
(次世代) |
ステレオカメラ |
ボンゴ(5代目) |
ダイハツからOEMを受けるボンゴ(=グランマックス)に標準装備。上記ダイハツの項目を参照。 |
| プリクラッシュブレーキ |
タイタン(6代目・2019年8月一部改良モデル以降) |
いすゞからOEMを受けるタイタン(=エルフ)に標準装備。下記いすゞの項目を参照。
当初は一部車型には搭載されていなかったが、2021年4月一部改良モデルから全車型標準装備。
2021年3月モデルまではエルフとは異なりオプションで装備レス化も可能であった。 |
| プリクラッシュブレーキ |
タイタン(7代目) |
いすゞからOEMを受けるタイタン(=エルフ)に標準装備。下記いすゞの項目を参照。
歩行者・自転車検知機能は全車標準装備。右左折時検知機能は一部グレードに搭載。 |
| レーダーブレーキサポート |
赤外線レーザー |
フレア(初代・前期型、レーダーブレーキサポート装着車)
フレアワゴン(2代目・前期型)
フレアクロスオーバー
キャロル(7代目・2018年12月一部改良以前)
スクラム(5代目・2019年7月一部改良以前)
スクラムワゴン(3代目・2019年7月一部改良以前) |
スズキからOEMを受けるフレア(=ワゴンR)とキャロル(=アルト)、スクラム(=エブリイ)は一部グレードに搭載、フレアワゴン(=スペーシア)とフレアクロスオーバー(=ハスラー)、スクラムワゴン(=エブリイワゴン)に標準装備。上記スズキの項目を参照。 |
| デュアルカメラブレーキサポート |
ステレオカメラ |
フレアワゴン(2代目・後期型)
フレアクロスオーバー(2015年12月一部改良モデル以降)
スクラム(5代目・2019年7月一部改良以降)
スクラムワゴン(3代目・2019年7月一部改良以降)
スクラムトラック(4代目・2019年9月一部改良以降) |
スズキからOEMを受けるフレアワゴン(=スペーシア)、スクラムワゴン(=エブリイワゴン)に標準装備、フレアクロスオーバー(=ハスラー)、スクラム(=エブリイ)、スクラムトラック(=キャリイ)は一部グレードに搭載。上記スズキの項目を参照。 |
| デュアルセンサーブレーキサポート |
赤外線レーダーとカメラ |
フレア(2代目(セーフティパッケージ装着車))
フレアワゴン(3代目)
キャロル(7代目・2018年12月一部改良以降) |
スズキからOEMを受けるフレア(=ワゴンR)にメーカーオプション、フレアワゴン(=スペーシア)に標準装備、キャロル(=アルト)の一部グレードに搭載。上記スズキの項目を参照。 |
| 三菱自動車工業 |
| 衝突被害軽減ブレーキシステム(FCM) |
ミリ波レーダー |
アウトランダー(2代目・前期型~後期型(2017年2月一部改良モデル以前)) |
「e-Assist」に含まれている衝突被害軽減ブレーキシステムは、相対速度30km/h以下で停止も可能。 |
| 衝突被害軽減ブレーキシステム(FCM)(歩行者検知タイプ) |
レーザーレーダーとカメラ |
アウトランダー(2代目・後期型(2017年2月一部改良モデル以降))
エクリプスクロス
デリカD:5(2019年2月ビッグマイナーチェンジ以降(ディーゼル車のみ)) |
5〜80km/hの範囲(歩行者に対しては5〜65km/hの範囲)で、前方に車または歩行者があるときにブザーとメーター内ディスプレイでブレーキ動作を促す。
また、衝突の可能性が高い時に緊急ブレーキを行うとブレーキアシストにより衝突速度を減速する。 |
| カメラ |
eKワゴン(3代目)(後期型(2018年5月一部改良モデル以降))
eKスペース(後期型(2018年5月一部改良モデル以降)) |
日産・デイズシリーズの姉妹車であるeKワゴン(=デイズ)、eKスペース(=デイズルークス)に搭載。上記日産の「エマージェンシーブレーキ(カメラ)」を参照。 |
衝突被害軽減ブレーキシステム(FCM)
(ステレオカメラタイプ) |
ステレオカメラ |
デリカD:2(2代目)
タウンボックス(3代目・2019年7月一部改良モデル以降)
ミニキャブバン(8代目・2019年7月一部改良モデル以降)
ミニキャブトラック(7代目・2019年9月一部改良モデル以降) |
スズキからOEMを受けるデリカD:2(=ソリオ)、タウンボックス(=エブリイワゴン)に標準装備。ミニキャブバン(=エブリイ)、ミニキャブトラック(=キャリイ)は一部グレードに搭載。上記スズキの「デュアルカメラブレーキサポート」を参照。 |
| 低車速域衝突被害軽減ブレーキシステム(FCM-City) |
ミリ波レーダー |
デリカD:2(初代・FCM-City装着車) |
スズキからOEMを受けるデリカD:2(=ソリオ)にメーカーオプション。上記スズキの「レーダーブレーキサポートII」を参照。 |
| 赤外線レーザー |
eKワゴン(3代目)(e-Assist搭載車、2015年10月一部改良モデル~後期型・2018年5月一部改良モデル以前)
eKスペース(e-Assist搭載車、2015年4月一部改良モデル~後期型・2018年5月一部改良モデル以前)
ミラージュ(6代目・2015年12月マイナーチェンジ以降) |
5〜30km/hで走行中、衝突の危険性が高い時、自律的にブレーキが作動し、追突などの危険を回避または衝突の被害を軽減する。eKシリーズは後に標準装備された。 |
タウンボックス(3代目・2019年7月一部改良モデル以前)
ミニキャブバン(8代目・2019年7月一部改良モデル以前) |
スズキからOEMを受けるタウンボックス(=エブリイワゴン)に標準装備。ミニキャブバン(=エブリイ)は一部グレードに搭載。上記スズキの「レーダーブレーキサポート」を参照。 |
| UDトラックス |
| トラフィックアイブレーキ |
ミリ波レーダー |
クオン(初代と2代目・2023年10月モデルまで) |
除雪車には設定なし。 |
| スマートトラフィックアイブレーキ |
ミリ波レーダーとカメラ |
クオン(2代目・2023年11月一部改良モデル以降) |
歩行者検知機能も備える。
除雪車には設定なし。 |
| プリクラッシュブレーキ |
ミリ波レーダーとカメラ |
コンドル(5代目・6代目) |
いすゞからOEMを受けるコンドル(=フォワード)に搭載。
5代目はGVW8t車・GVW11t車に標準装備、GVW7.5t車・GVW14t車はメーカーオプションとなっていたが、6代目は全車型標準装備。
下記いすゞ自動車の項目を参照。 |
| プリクラッシュブレーキ |
ステレオカメラ |
カゼット(3代目) |
いすゞからOEMを受けるカゼット(=エルフ)に搭載。
歩行者・自転車検知機能は全車標準装備。右左折時検知機能はオプション設定。下記いすゞ自動車の項目を参照。 |
| 日野自動車 |
| PCS (プリクラッシュセーフティ)[衝突被害軽減ブレーキシステム] |
ミリ波レーダーと画像センサー |
プロフィア
セレガ(2代目・2010年7月一部改良モデル以降)
レンジャー(6代目・2021年7月モデルまで)
デュトロ(2代目・2016年4月一部改良モデル以降から2020年4月モデルまで) |
プロフィア・セレガ・レンジャーは全車型に、デュトロはLPG車を除く全車型にそれぞれ標準装備。
車両検知機能の他にもプロフィア(3代目)・セレガ(2代目・2017年7月一部改良モデル以降)・レンジャー・デュトロには歩行者検知機能も備える。
プロフィア(2代目・2014年4月一部改良モデル以降と3代目)・セレガ(2014年4月一部改良モデル以降)・レンジャーはドライバーモニターと車両ふらつき警報(レンジャーは一部車型ではドライバーモニターと車両ふらつき警報はメーカーオプション)と連動し、ドライバーの状態や車両のふらつき状態によっても作動する。 |
| PCS (プリクラッシュセーフティ) |
ミリ波レーダーと画像センサー |
レンジャー(6代目・2021年8月一部改良モデル以降)
メルファ(2021年10月一部改良モデル以降)
デュトロ(2代目・2020年5月一部改良モデル以降) |
昼間・夜間の歩行者検知機能、昼間の自転車検知機能も備える。 |
| PCS (プリクラッシュセーフティ)[衝突被害軽減ブレーキシステム] |
ミリ波レーダーとカメラ |
リエッセII(2代目・2018年6月一部改良モデル以降) |
トヨタからOEMを受けるリエッセII(=コースター)の全グレードに搭載。幼児専用車には当初は設定していなかったが、2021年1月一部改良モデルから標準装備。
上記トヨタの項目を参照。 |
| いすゞ自動車 |
| プリクラッシュブレーキ |
ミリ波レーダーとカメラ |
ギガ(初代・2007年10月一部改良モデル以降と2代目・2019年11月モデルまで)
フォワード(5代目・2015年11月一部改良モデルから2020年12月モデルまで) |
ギガは当初は一部車型のみの設定であったが、2014年11月一部改良モデルから全車型に標準装備。
フォワードはGVW8t車(210ps・240psエンジン搭載車)・GVW11t車に標準装備。GVW7.5t車・GVW8t車(190psエンジン搭載車)・GVW14t車・GVW16t車・GVW20t車はメーカーオプション。
フォワードは全駆、CNG車には設定なし。 |
| プリクラッシュブレーキ |
ミリ波レーダーとカメラ |
ギガ(2代目・2019年12月一部改良モデル以降、セミトラクタは2023年3月モデルまで)
フォワード(5代目・2021年1月一部改良モデル以降と6代目) |
歩行者・自転車検知機能も備える。 |
| プリクラッシュブレーキ |
ミリ波レーダーとカメラ |
ギガ トラクタ(3代目) |
UDとの共同開発車種であるギガ トラクタ(3代目)に搭載。上記UDの項目を参照。 |
| プリクラッシュブレーキ |
ステレオカメラ |
エルフ(6代目・2018年10月一部改良モデル以降) |
歩行者・自転車検知機能も備える。
当初は一部の車型はメーカーオプションもしくは未設定であったが、2021年3月一部改良モデルから全車型に標準装備された。 |
| プリクラッシュブレーキ |
ステレオカメラ |
エルフ(7代目) |
全車型に設定されている安全性能パッケージによって機能が異なる。
標準装備のBASICパッケージは直進時の歩行者・自転車検知機能も備える。
メーカーオプションのPREMIUMパッケージ、ADVANCEパッケージ、STANDARDパッケージは直進時の歩行者・自転車検知機能の他にも右左折時検知機能も備える。 |
| 衝突被害軽減ブレーキシステム |
ミリ波レーダーと画像センサー |
ガーラ(2代目・2010年8月一部改良モデル以降)
ガーラミオ(2代目・2021年9月一部改良モデル以降) |
日野・セレガとの統合車種であるガーラ(2代目)並びに日野・メルファとの統合車種であるガーラミオ(2代目)に搭載。上記日野の項目を参照。 |
| プリクラッシュブレーキ |
ミリ波レーダー |
コモ(2代目・2018年7月一部改良モデル以降) |
日産からOEMを受けるコモ(=NV350キャラバン バンDX)に搭載。上記日産の項目を参照。 |
| 三菱ふそうトラック・バス |
| AMB(衝突被害軽減ブレーキ) |
ミリ波レーダー |
スーパーグレート(初代)
エアロクィーン(2013年1月一部改良モデル以降〜2017年5月一部改良モデル以前)
エアロエース(2013年1月一部改良モデル以降〜2017年5月一部改良モデル以前) |
|
| アクティブ・ブレーキ・アシスト4(ABA4)/AMB Plus |
ミリ波レーダー |
スーパーグレート(2代目・2019年9月モデルまで) |
アクティブ・ブレーキ・アシスト4は歩行者検知機能も備える。
アクティブ・ブレーキ・アシスト4はプロ・ライン、プレミアム・ラインに搭載。AMB Plusはエコ・ラインに搭載。 |
| アクティブ・ブレーキ・アシスト5(ABA5) |
ミリ波レーダーとカメラ |
スーパーグレート(2代目・2019年10月一部改良モデル以降) |
歩行者検知機能も備える。 |
| アクティブ・ブレーキ・アシスト3(ABA3) |
ミリ波レーダー |
エアロクィーン(2017年5月一部改良モデル以降)
エアロエース(2017年5月一部改良モデル以降) |
|
| Advanced Emergency Braking System(AEBS) |
ミリ波レーダー |
キャンター(8代目・2018年8月一部改良モデル以降) |
歩行者検知機能も備える。
GVW7.5t超車、全駆、ハイブリッド車には設定無し。 |
| 名称 |
センサ |
搭載車種 |
解説 |
| メルセデス・ベンツ |
| CPA(衝突警告システム) |
レーダーセンサー |
Aクラス
Bクラス |
CPAは自律的にブレーキで衝突被害軽減、回避は行わず、警告、ブレーキアシストのみ行う。 |
| CPAプラス(緊急ブレーキ機能) |
「セーフティパッケージ」に含まれているCPAプラスは、最大ブレーキの約60%で自律的に緊急ブレーキが作動し、衝突の回避もしくは被害軽減をサポートする。 |
| PRE-SAFEブレーキ |
レーダーセンサー |
Eクラス(4代目・2011年11月マイナーチェンジ以降)
Sクラス
Cクラス(3代目・2013年1月マイナーチェンジ以降) |
「レーダーセーフティパッケージ[74]」に含まれているPRE-SAFEブレーキは、200km/h以下で被害軽減ブレーキで衝突被害軽減、30km/h未満で衝突回避をサポートする。
2013年5月14日にEクラスがマイナーチェンジされ、PRE-SAFEブレーキがカメラとレーダーの複合式となり、今まで苦手とされていた歩行者検知能力が強化された。 |
| レーダーセンサーとカメラ |
Eクラス(4代目・2013年5月マイナーチェンジ以降)
Sクラス(6代目)
Cクラス(4代目) |
| BMW (MINI) |
| 前車接近警告機能(衝突被害軽減ブレーキ付) |
レーダーセンサー |
3シリーズ
5シリーズ
6シリーズ(全て2013年8月マイナーチェンジ以前) |
衝突被害軽減ブレーキは、衝突の危険がある場合には軽度のブレーキをかけ自動減速させることで、被害を軽減させる。 |
| 衝突回避・被害軽減ブレーキ |
カメラ |
ミニ
2シリーズ アクティブツアラー
3シリーズ |
自律的にブレーキを掛けて衝突を回避または被害の軽減を図る。 |
| レーダーセンサーとカメラ |
1シリーズ(F20/F40)2013年8月~オプション、2015年5月~素の118以外は標準搭載
3シリーズ
5シリーズ
7シリーズ |
| 衝突回避・被害軽減ブレーキ(事故回避アシスト付) |
レーダーセンサーとカメラまたはステレオカメラ |
5シリーズ(G30/G31)
7シリーズ(G11/G12)
8シリーズ(G14/G15) |
ブレーキによって衝突が回避できないとドライバーが判断し、ステアリングでの回避動作に入った場合は、システムが周囲の状況を判断し、ステアリングの操作力にも介入する。 |
| レーダーセンサーと三眼カメラ |
3シリーズ(G20)
5シリーズ(G30/G31)2020年9月マイナーチェンジ~
7シリーズ(G11/G12)2019年6月マイナーチェンジ~
8シリーズ(G14/G15)2019年5月マイナーチェンジ~
X5(G05)
X7(G07) |
ブレーキによって衝突が回避できないとドライバーが判断し、ステアリングでの回避動作に入った場合は、システムが周囲の状況を判断し、ステアリングの操作力にも介入する。3眼カメラ化により歩行者の検知性能がアップしている |
| ボルボ |
| インテリセーフ |
赤外線レーザー、ミリ波レーダー、カメラ |
ボルボ・全車種 |
200km/h以下の場合に作動。
車両等とは60km/h以下、歩行者とは45km/h以下、自転車とは50km/h以下であれば自律的なブレーキで衝突回避も可能。
大型動物とは最大-0.3Gの加速度により衝突回避を支援。
交差点内で右折(右側通行の場合は左折)する際、対向車の動向を監視し、衝突の危険を検知すると自律的なブレーキが作動する機能(インターセクションサポート)を搭載している。
車両後方にも搭載されているレーダーが後続車の急接近を検知すると、ハザードランプを通常より早く点滅させ後続車に警告を与え、更に追突の危険が切迫するとシートベルトを締めつけてむち打ち症のリスクを軽減し、自車が停止している場合はブレーキ制動を最大に作動させ、玉突き事故による2次被害の発生を防ぐ機能(静止時オートブレーキ機能付被追突時警告機能)を搭載している。
完全に停止する被害軽減ブレーキや歩行者を検知する被害軽減ブレーキ、二輪車を検知する被害軽減ブレーキ、インターセクションサポート、大型動物を検知する被害軽減ブレーキを世界で初めて搭載した[75]。被害軽減ブレーキなどの全車種標準装備も世界で初めて行った。EURO NCAPが行う被害軽減ブレーキの試験において唯一の満点を有している。 |
| フォルクスワーゲン |
| シティエマージェンシーブレーキ |
レーダーセンサー |
CC
up!
ゴルフ(7代目) |
30km/h未満で作動。自律的なブレーキで衝突の回避・衝突被害の軽減を図る。 |
| フロントアシスト(Front Assist) |
ミリ波レーダー |
ゴルフ(7代目)
ポロ(5代目後期型)
パサート |
全速度域で作動し、自律的にブレーキで減速して衝突被害軽減を行う。5~30km/h未満ではシティエマージェンシーブレーキが作動し、衝突の回避・衝突被害の軽減を図る。
2017年5月にマイナーチェンジされたゴルフ(7代目)から歩行者検知が追加された。5~65km未満で走行中に歩行者検知機能が作動する。 |
| フィアット |
| シティブレーキコントロール |
赤外線レーザーセンサー |
パンダ4x4 |
30km/h未満で走行中に、追突する可能性がある場合に、自律的にブレーキを作動させ、追突の回避や追突時の衝撃軽減をサポートする。 |
| 前面衝突警報(クラッシュミティゲーション付) |
レーザーセンサーとカメラ |
500X |
走行中に、追突する可能性がある場合に、自律的にブレーキを作動させ、追突の回避や追突時の衝撃軽減をサポートする。 |
| アルファロメオ |
| 前面衝突警報付自動緊急ブレーキ |
ミリ波レーダーとカメラ |
ジュリア
ステルヴィオ |
200km/h以下の場合に作動。歩行者に対しては50km/h未満(ステルヴィオは65km/h未満)であれば自律的なブレーキで衝突回避も可能。 |
| プジョーシトロエン (DS オートモビル) |
| アクティブシティブレーキ |
赤外線レーザーセンサー |
DS3、208(A9) |
30km/h未満での走行中に、追突する可能性がある場合に、自律的なブレーキを作動させ、追突の回避や追突時の衝撃軽減をサポートする。 |
| エマージェンシーブレーキサポート |
|
308(T7)、308(T9前期) |
作動速度は10キロ~で対応物は前を走る車両、最大約20キロの減速 |
| アクティブセーフティブレーキ |
|
208(P21 STYLE) |
作動範囲は約5~80km/h以下(二輪車、夜間検知機能なし) |
|
308(T9後期)、3008(P84) |
作動範囲は約5~140km/h。約80km/h 以下では停止車両を、約60km/h 以下では歩行者も検知して追突事故などの危険を回避、あるいは衝突の被害を軽減。 |
| アクティブセーフティブレーキⅡ |
|
208(P21 STYLEを除く)、2008(P24)、508(R8)、5008(P87) |
作動範囲は約5~140km/h。約80km/h 以下では停止車両を、約60km/h 以下では歩行者も検知して追突事故などの危険を回避、あるいは衝突の被害を軽減。検知するカメラの精度を上げることで、二輪車や夜間走行の検知能力も高めています。 |
| ルノー |
| アクティブエマージェンシーブレーキ |
フロントガラス中央上部のカメラとフロントバンパー内のレーダーセンサー |
ルーテシア(2020(令和2)年11月 発売)
メガーヌ 2021(令和3)年8月マイナーチェンジ~ |
前方の車両や、歩行者・自転車に衝突する可能性を感知し、アラーム音や表示灯による警告を行う。さらに衝突の危険が高まると、ドライバーのブレーキ操作をサポートし、衝突時の被害や衝撃を軽減するサポートを行う。(検知対象:前方を同一方向に走行する車両〈約7 ~ 170km/hでの走行時〉/ 静止車両・歩行者・自転車〈約7 ~ 80km/hでの走行時〉) |
| ゼネラルモーターズ |
| オートマチック ブレーキ |
レーダー |
ATS |
前進のみではなく後退でも自律的にブレーキをかける[76]。 |
| フォード・モーター |
| アクティブ・シティ・ストップ |
赤外線レーザーセンサー |
フォーカス
クーガ
フィエスタ |
30km以下での低速走行時に、前方の車両との追突の危険性を感知すると自律的にブレーキをかけて追突を未然に回避、ないしは衝突ダメージを軽減する。 |
| ジープ |
| 前面衝突警報(クラッシュミティゲーション付) |
レーザーセンサーとカメラ |
レネゲード
コンパス(2代目)
グランドチェロキー |
前方の車両との追突の危険性を感知すると自律的にブレーキをかけて追突を未然に回避、ないしは衝突ダメージを軽減する。 |
| 前面衝突警報(クラッシュミティゲーション、歩行者検知機能付) |
レーザーセンサーとカメラ |
チェロキー(5代目・2019年モデル) |
前方の車両および歩行者との追突の危険性を感知すると自律的にブレーキをかけて追突を未然に回避、ないしは衝突ダメージを軽減する。 |