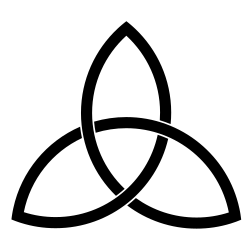トップQs
タイムライン
チャット
視点
桂藤兵衛
ウィキペディアから
Remove ads
桂 藤兵衛(かつら とうべえ)は、落語の名跡。もとは上方落語の名跡だった。当代は東京の落語家で3代目を名乗る。
月亭春松編の『落語系圖』は、元川傳吉の桂藤兵衛を2代目としている[1][2]。しかし、『古今東西落語家事典』は、元川傳吉の桂藤兵衛について「墓石・新聞記事・その他の資料はすべて『三代目』となっており、今はこれにしたがう」として、3代目に扱っている[2]。この項では、便宜上、元川傳吉の桂藤兵衛を上方3代目とし、当代を東京3代目とする。
上方3代目
3代目 桂 藤兵衛(かつら とうべえ、1849年(嘉永2年) - 1902年(明治35年)5月31日[4][注釈 1])は、明治期の上方落語の落語家(上方噺家)。本名∶元川 傳吉[4]。
経歴
大坂安治川通三丁目の米屋の子として生まれる[4]。幼名は龜吉[4]。
17、8歳の頃、初代桂文枝の男衆に入り、文馬を名乗り九郎右衛門町の大富という席で前座に出る[4]。数年後文車と改名[要出典]。
その後東京へ赴いた時期があり、大阪に戻ってから初代桂文之助門下となり文字助を名乗る[4]。1885年3月、3代目桂藤兵衛と改名する[4]。以降、京都・新京極の幾代亭に長く出演して、「桂藤兵衛藤原忠勝入道
1898年夏、同じ新京極の笑福亭に移籍[4]。1900年正月、大阪に出て、西國坊明學と組んで「藤兵衛」の「藤」と「明學」の「明」に因んで「藤明派」を立ち上げ、桂派・三友派と張り合うが、翌年秋ごろ、心臓の病で体調を崩して京都へ戻り、1902年に六角富小路下ルの自宅で病没[4]。享年54(一説に51)[4]。
活動
「顋無齋」の名乗りの通り、顎が短かかった[4]。加えて、眉太、色黒で、『古今東西落語家事典』は「木魚に目鼻をつけたような顔」と評している[4]。
木遣崩し、鎌倉節、オッペケペー節、郭巨の釜堀(テケレッツのパー)などをはやらせ、『三十石』の舟唄を得意としたという[4]。
弟子
Remove ads
江戸3代目
3代目 桂 藤兵衛(かつら とうべえ、1952年1月13日[5] - )は、東京都文京区出身の落語家。本名∶上 弘明[5]。落語協会所属。出囃子は『青すだれ』。
経歴
1969年6月に8代目林家正蔵(のち林家彦六)に入門、前座名は「林家上蔵」[5]。この「上蔵」の名前はかつて4代目林屋正蔵が名乗っていたことがある[6]。
1974年9月に二ツ目昇進[5]。1981年12月に国立演芸場花形若手演芸会新人賞金賞を『そば清』で受賞[要出典]。1982年1月、師匠の彦六が死去[7]。弟弟子林家正雀とともに兄弟子2代目橘家文蔵一門に移籍した[5]。1983年4月に正雀が先に真打に昇進した[5]。
1984年9月に林家種平、古今亭八朝とともに[要出典]真打に昇進し、3代目桂藤兵衛を襲名した[5]。1986年3月、国立演芸場 花形若手演芸会新人賞金賞を『竹の水仙』で受賞[要出典]。
人物
受賞歴
演目
※二重カギ括弧は省略。
Remove ads
脚注
参考文献
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads