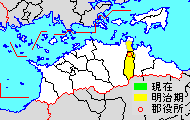トップQs
タイムライン
チャット
視点
三木郡
日本の香川県(讃岐国)にあった郡 ウィキペディアから
Remove ads
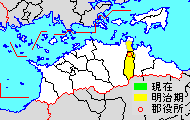
郡域
1878年(明治11年)当時の郡域は、現在の行政区画では概ね以下の区域に相当する。
郡名の由来
讃岐国高松藩の地誌である『全讃史』(中山城山[注 1] 著、1828年(文政11年)に成立)には「井戸高木に上古むろの大木あり、その高さ数十丈、よってその地を高木といい、平木に柊の古木あり、よってその地を平木といい、朝倉に山椒の大樹あり、朝日をさえぎってその里くらし、よって朝倉の里といい、朝倉山椒というもこれにより出づ。この三木あるを以て、三木郡といえり」[1][2]と記されている。
歴史
要約
視点
古代
郷
- 井門(いど)郷 - 三木町大字井戸(いど)
- 高岡(たかおか)郷 - 三木町大字上高岡(かみたかおか)、三木町大字下高岡(しもたかおか)
- 氷上(ひかみ)郷 - 三木町大字氷上(ひかみ)
- 田中(たなか)郷 - 三木町大字田中(たなか)
- 井上(いのへ)郷 - 三木町大字井上(いのうえ)、三木町大字平木(ひらぎ)、三木町大字鹿伏(ししぶせ)
- 池辺(いけのへ)郷 - 三木町大字池戸(いけのべ)
- 武例(むれ)郷 - 高松市牟礼町牟礼(むれちょうむれ)
- 幡羅(はら)郷 - 高松市牟礼町原(むれちょうはら)
- 山下里
『和名抄』にない山下里は、平城宮の東院南門(推定建部門)外の溝跡から発見された荷札と考えられる木簡に「讃岐国三木郡山下里」と記されていた。溝の年代により、奈良時代前半にはあったと推定される[4]。
式内社
近代
- 牟礼村、大町村、原村、池戸村、井上村、平木村、鹿伏村、田中村、下高岡村、氷上村、井戸村、上高岡村、西鹿庭村、東鹿庭村、西朝倉村、東朝倉村、西小蓑村、東小蓑村、西奥山村、東奥山村
- 1871年(明治4年)
- 1873年(明治6年)2月20日 - 名東県の管轄となる。
- 1874年(明治7年)(16村)
- 西鹿庭村・東鹿庭村が合併して鹿庭村となる。
- 西朝倉村・東朝倉村が合併して朝倉村となる。
- 西小蓑村・東小蓑村が合併して小蓑村となる。
- 西奥山村・東奥山村が合併して奥山村となる。
- 1875年(明治8年)9月5日 - 香川県(第2次)の管轄となる。
- 1876年(明治9年)8月21日 - 第2次府県統合により愛媛県の管轄となる。
- 1878年(明治11年)12月16日 - 郡区町村編制法の愛媛県での施行により、行政区画としての三木郡が発足。「三木山田郡役所」が池戸村に設置され、山田郡とともに管轄。
- 1881年(明治14年) - 「三木山田郡役所」の廃止により「大内寒川郡役所」(寒川郡津田村)が「大内寒川三木郡役所」に改組され、大内郡・寒川郡とともに管轄。
- 1888年(明治21年)12月3日 - 香川県(第3次)の管轄となる。

備考
行政
- 三木・山田郡長
- 愛媛県大内・寒川・三木郡長
- 香川県大内・寒川・三木郡長
脚注
参考文献
関連項目
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads