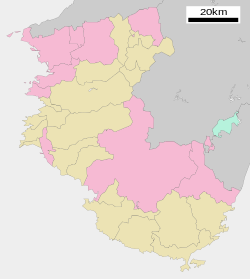トップQs
タイムライン
チャット
視点
宝亀院
和歌山県伊都郡高野町高野山にある高野山真言宗の別格本山の寺院 ウィキペディアから
Remove ads
宝亀院(ほうきいん)は、和歌山県伊都郡高野町高野山にある高野山真言宗の別格本山の寺院。本尊は十一面観音。宿坊。御衣寺(おころもでら)宝亀院とも呼ばれる。新西国三十三箇所第6番札所。
ユネスコの世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成要素。
歴史
寺伝によると、延喜21年(921年)10月21日の夜に醍醐天皇の枕元に、突如として髪や髭が伸び放題で袈裟や衣も汚れて破けている姿の空海が現れた。そして「高野山 結ぶ庵に 袖朽ちて 苔の下にぞ 有明の月」と歌うとその姿を消してしまった[1]。驚いた醍醐天皇は以前から東寺長者の観賢僧正が空海に大師号を授けてほしいと訴えていた事もあり、10月27日に空海に弘法大師の号を授け[1]、中納言藤原扶閑を勅使として高野山に遣わしたという。
すると、11月5日の暁になって高野山奥の院の空海御廟の前で祈っていた観賢の眼前に、髪や髭は伸び放題で袈裟や衣も汚れて破けている空海が現れた。そこで観賢は空海の髪や髭を剃って奇麗にし、新しい袈裟と衣に着替えてもらった。すると空海は喜んだのか消えてしまったという。これ以来、毎年空海の命日である3月21日に新しい衣を奥の院の弘法大師御廟に供えている[1]。
この報告を受けた醍醐天皇はさっそく観賢を開山として高野山内に勅願寺を建立することにし、空海が宝亀5年(774年)6月15日に生まれたことから寺は宝亀院と名付けられた、これが当寺の建立の由来であるという[1]。
Remove ads
境内
文化財
重要文化財
その他
行事
前後の札所
所在地
- 和歌山県伊都郡高野町294
アクセス
脚注
参考文献
外部リンク
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads