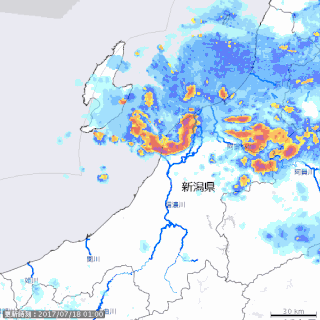トップQs
タイムライン
チャット
視点
線状降水帯
強い降水を伴う線状の雨域 ウィキペディアから
Remove ads
線状降水帯(せんじょうこうすいたい)とは、日本周辺で[1]集中豪雨発生時に気象レーダー画像や解析雨量分布によくみられる線状の降水域を指す用語[2]。次々に発生する発達した雨雲が線状に列をなして連なり、組織化して数時間にわたってほぼ同じ場所にかかり続け、局所的に強い雨を持続的に降らせることにより、しばしば土砂災害や低地での内水氾濫、河川からの外水氾濫など[3]の甚大な災害をもたらす[1]。
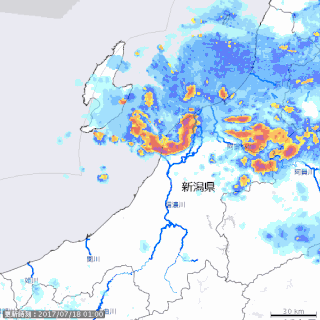
用語の定義と歴史
要約
視点
線状降水帯
日本の気象庁では、線状降水帯を「次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50–300km程度、幅20–50km程度の強い降水をともなう雨域」と定義し、天気予報等で用いる予報用語として採用している[4]。一方、専門家の間でもさまざまな定義が用いられており[4]、気象学の専門用語とみなされてはいるものの[5]、学術的に厳密な定義がなされた用語ではない[1][6]。前記の気象庁による量的な定義も厳密なものではなく[1]、「集中豪雨」と同様に統一的な定義はない[7][8]。ただし、気象庁が線状降水帯に関する防災気象情報(顕著な大雨に関する情報)を発表するにあたっては、その発生を判定する基準として、運用の便宜上、厳格な定量的基準が定められている[9](基準の詳細は後述)。このように「線状降水帯」は、防災上の観点から使われる用語としても役立てられている側面がある[3]。
1980年代後半に気象庁が全国20か所に展開する気象レーダーの観測データがデジタル化され、それらを重ね合わせて合成した全国規模の雨雲レーダーが運用されるようになった[10][11]。1990年代に入って、雨雲レーダーのデータにアメダスなどの雨量計で観測した降水量の実測値を加味して補正した1時間降水量(解析雨量)データが作成されるようになり[10][12]、大雨時の解析雨量分布の調査研究が進んだことから、線状の降水域(雨雲)の存在が知られるようになった[10][13]。そして2000年頃から、気象庁気象研究所のメソ気象研究者を中心に[14]、九州地方で発生する地形性の線状の降水系(後述)を対象として、「線状降水帯」という用語が使われ出した[7]。その後の研究により、九州以外や地形に起因しない線状の降水域の存在が複数確認され[7]、2007年に出版された研究者向けの教科書『豪雨・豪雪の気象学』の中で初めて、現在とほぼ同じ定義の用語として使用されたとされる[12][14][15]。気象研究所の報道発表資料で初めて用いられたのは、平成23(2011)年7月新潟・福島豪雨の際、その発生要因として示されたものである[12][16]。その後、平成26(2014)年8月豪雨による広島市の土砂災害の発生時にマスコミ報道で多く取り上げられ、広く一般にも認知されるようになった[12]。2022年6月からは気象庁が線状降水帯の予測を行うようになり、耳にする機会は多くなっている[17]。
「線状降水帯」の名は、集中豪雨発生時によくみられる線状の降水域という見た目の特徴に由来するが[2]、レーダーエコーが線状に見えた場合でも、寒冷前線などに伴って移動する線状の雨域(降雨バンド)は、線状降水帯を形成することはなく、通常この名称でよばれることはない[1]。他方で、小林 (2023)では、より概念を広く捉えて、「次々と発生した積乱雲が列をなすことで組織化された積乱雲群」で「線状という形態を満たすもの」を一般に線状降水帯とよび、広義の線状降水帯には、寒冷前線に伴う積乱雲列、スコールライン、マルチセル、バックビルディングなど、さまざまな環境条件による形態が含まれ、実際の積乱雲の構造も多種多様であると説明し、本来のバックビルディング型の積乱雲列を狭義の線状降水帯とよんでいる[18]。
なお、英語圏では「線状降水帯」に相当する適切な概念がないために英訳は定まっておらず[1][6]、レビュー論文(Kato 2020)では “senjo-kousuitai” と記載されている。
テーパリングクラウド
→詳細は「テーパリングクラウド」を参照
線状降水帯という用語が登場する以前[13]、気象衛星画像から確認できる細長く先の尖った雲の形状を指して、テーパリングクラウド(にんじん状の雲)という用語も、2010年頃の時点では日本において盛んに使用されていたが、2023年現在は気象用語としては使われなくなっている[19]。一地点で新しい積乱雲が次々と発生し、風下へ流され、発達するにつれ幅が広がっていく、その発生メカニズムはバックビルディングとよばれ、線状降水帯とメカニズムが一致している[20]。ただし、衛星画像を通して見えるのは積乱雲の雲頂部分(かなとこ雲)だけであり[21]、厳密な意味では線状降水帯とテーパリングクラウドは一致しない[22]。
→「§ バックアンドサイドビルディング型」も参照
Remove ads
現象の概説
要約
視点
線状降水帯の実体は、鉛直方向に発達した対流雲である積乱雲(セル[注 1])の組織化された集合体である[2][23]。水平スケールにして50–300km程度[24]のメソ対流系の一種とされ[2]、時間スケールは3時間を超える場合もある[24]。およそ20–200kmのメソβスケールに相当する[24]中小規模の大気現象であり、全体像は気象衛星から、内部構造は気象レーダーで捉えられる[25]。
その形態については、内部構造の違いにより、バックビルディング型、バックアンドサイドビルディング型、スコールライン型の大きく3つの型に分類される[26]。典型的なバックビルディング型の線状降水帯では、3–5個程度の個々の積乱雲(シングルセル)で線状の積乱雲群(マルチセル)を組織し、さらに複数の積乱雲群が連なることによって線状降水帯を形成する過程で、積乱雲→積乱雲群→線状降水帯という階層構造がみられる事例もある[27]。
形態と構造
線状降水帯の形態と維持メカニズムについて系統的な研究を行った瀬古 (2010)では、下節の3つの型が提案されている[26]。3つの型に共通する重要な点は、
- 降水域から発散する気流と下層インフローが収束して新しい対流セルを発生させること
- 対流セルが中層風により移動すること
で、維持メカニズムについて詳しくみると、
- 相当温位の高い下層インフローが対流セルの発散流と収束して上昇すること
- 1.の収束が降水帯から大きく離れないこと
- 降水が下層インフローによる高相当温位の気塊の供給を妨げないこと
の3点でも共通していた[28]。
バックビルディング型
→「集中豪雨 § バックビルディング型」も参照
バックビルディング(BB)型は、線状降水帯の代表的な形成過程の一つで[29]、対流の発生ポイントに吹き込んで大量の水蒸気を供給する下層風(模式図で示した水平方向の赤い矢印)と、対流セルをライン状に押し流す中層風(同じく水平方向の青い矢印)の風向が同じ方向なのが特徴である[30]。対流セルからの発散と流れ込む下層風とが収束(青い矢印と赤い矢印が合流)して[31]、下層風の上流側(風上側)となる降水帯の先端部に新しいセルが次々と発生し、それらが発達しながら降水帯に沿って下流側(風下側)に移動して雲列をなし[32]、進行方向前方のセルと組織化することにより、全体として線状降水帯を形成する[33]。進行方向の後方(バック)に背の高い積乱雲が次々と並び立つ(ビルディングする)ことから、この名が付いた[34]。降水帯の先端で発生した対流セルは風下側に移動して衰弱するが、また先端の同じ場所に新しい対流セルが発生する[35]。このように降水帯内部では対流セルが発生と消滅を繰り返して世代交代が進む一方で、降水帯全体としてみると、積乱雲の列が同じ場所に停滞する定常な状態となっている[35]。その結果、積乱雲の発生地点の風下となる極めて局所的な線状のエリアで記録的な豪雨が続き、災害が発生する危険性がある[36]。バックビルディング型では、降水系全体の移動速度が遅いことも、しばしば集中豪雨の原因となる[35]。
過去に日本で確認された線状降水帯では、2014年8月20日に広島豪雨災害を引き起こした事例がバックビルディング型の典型例である[33]。過去には3時間で200mmを超える大雨をもたらし、1時間平均でも100mm以上の猛烈な雨を記録した事例も複数あった[37]。
→「§ 線状降水帯による大雨の主な事例」も参照
バックアンドサイドビルディング型
バックアンドサイドビルディング(BSB)型は、中層風と下層風の風向が直交するのが特徴で[30][38]、対流は中層風の風上側(バック)で発生し[30]、対流セルは中層風で流されて風下側に移動するが[30]、下層風は積乱雲群の側面(サイド)から流入し[38]、対流セルからの発散と収束して、進行方向左側で新しい対流セルが繰り返し発生・強化される[30]。BSB型では積乱雲群が側面から流されながら移動するため、線状というよりも面的に広がった[39]、いわゆる「にんじん状の雲(降水域)」となりやすい[40]。
スコールライン型
スコールライン(SL)型は、熱帯域やアメリカ中西部で多く観測されるスコールラインと同じ特徴をもつ型で[41]、進行方向前面に発生する対流性の強い降水域と、後面に広がる層状性の弱い降水域とを併せ持つ[42][43]。積乱雲が数百キロメートルのスケールで弧状に並んだ形態をしたメソ対流系の一種で、降水帯の移動速度が速い点も特徴の一つである[43]。乾燥した中層風が下層風とは逆方向(後面側)から貫入する際に組織化し、降水帯は下層風に直交する方向に伸びる[44]。強い降水域は降水帯の前面に沿って連続的に分布する[44]。日本付近ではSL型の発生数は少ない[41]。
発生条件
線状降水帯が発生する条件は完全には解明されていないが、いくつかの条件が重なると線状降水帯が発生しやすいことが知られている[45][46]。加藤 (2024)は、線状降水帯が発生するための必要条件として、次の4つを挙げている[47]。
- 「大雨の素」となる大量の水蒸気が継続して大気下層に流入すること
- 積乱雲が発生・発達するために、流入する空気が暖かく湿っていること
- 積乱雲が背高く発達するために、大気中層が湿っていること
- 複数の積乱雲が組織化するために、適度な鉛直シアが存在していること
また、Kato (2020)は、線状降水帯によるものと考えられる過去の複数の大雨事例から、その発生に必要な6つの量的な条件[46][48]を見出した[49]。
- 水蒸気供給: 500 m高度のFLWV(水蒸気フラックス量)≧150 gm-2s-1
- 対流発生: 500 m高度の空気塊を持ち上げたときのDLFC(自由対流高度までの距離)<1000 m
- 対流発達: 500 m高度の空気塊を持ち上げたときのLNB(EL)(浮力がなくなる高度(平衡高度))≧3000 m
- 上空の湿度: 500 hPaと700 hPa気圧面のRH(相対湿度)≧60%
- 上昇気流域: 700 hPa気圧面、400 km水平四方で平均したW(鉛直速度)≧0 m⋅s−1
- 鉛直シア: SREH(ストームに相対的なヘリシティ)≧100 m2s-2
→「雷雨 § 雷雨の指数」も参照
1.は大雨をもたらす下層水蒸気を供給する条件を設定したもので、150 gm-2s-1の水蒸気フラックス量は、高度1 kmまで水蒸気の流入量が同値で継続し、その半分が幅30 kmの領域に雨として降って地上に落下したとき、1時間降水量が100 mmに近い値となるように設定した閾値である[49]。
2.と3.は積乱雲の発生しやすさと発達の条件として設定したものである[48]。3.は積乱雲の発達高度を想定したものではなく、大気中下層に暖気が流入した場合に積乱雲の発達が抑制されるケースを除外するための条件設定である[50]。
4.は上空の湿りを判断するための条件で、60%という閾値は熱帯域の積乱雲の発達条件とも整合する[50]。
5.はメソスケールの対流雲(積乱雲)の発生域の影響を除外して、総観スケールの上昇気流場を判断するために必要な鉛直流の速度を示したものである[50]。
6.は3次元の鉛直シア[注 2]の効果を評価するのによく用いられる、SREH(ストームに相対的なヘリシティ)という指数の設定値である[50]。
これら6つの条件の中でも、1.と2.は大雨の発生を診断する際に最も重要な気象要素の一つとされる[52]。
地形の影響
また、山岳地形によって空気塊が強制上昇すると、容易に対流が発生して大雨の発生を助ける要因となる[53]。そのため、前記の6つの条件を満たさない場合でも、線状降水帯による大雨が発生することがある[54]。たとえば、九州西岸では島嶼や半島、湾などの地形の影響で南西風が収束しやすく、同じパターンの線状の降水系が幾度も観測されている。それらの特定の線状降水域には、下記のように固有の呼称でよばれるものがある。
環境条件

線状降水帯の発生する環境条件を総観スケールでみると、梅雨期の日本付近には、太平洋高気圧に伴う温暖・湿潤な気団(小笠原気団)と、中国大陸からオホーツク海高気圧にかけての相対的に乾燥・寒冷な気団(オホーツク海気団)との間に風の収束帯が形成される[83]。この収束帯は梅雨前線帯[注 3]とよばれ、その南縁付近に水蒸気分布が濃く、大気の安定度が相対的に低い、東西に伸びた湿舌とよばれる舌状の形状をした湿潤域を形成する[85][86]。線状降水帯に伴う大雨は、この領域周辺で発生することが多い[56]。
→「§ 大気の川」も参照
統計的な傾向
津口・加藤 (2014)と同じ客観的な抽出方法[87]を用いたKato (2020)によれば、1989年から2015年までの日本における集中豪雨事例のうち、線状降水帯がみられた事例[注 4]は約半数である[88]。降水系が移動する台風や熱帯低気圧本体の周辺では、集中豪雨に対する線状降水帯の割合は3分の1と小さくなり、反対に停滞前線付近では、その割合は最も大きく、3分の2を超える[89]。台風・熱帯低気圧本体周辺を除くと、集中豪雨事例の3分の2で線状降水帯が発生していることになる[89]。地方別にみると、東日本・北日本では集中豪雨に対する線状降水帯の割合は4割程度と小さいのに対し、四国や九州では6割を超える[88]。月別にみると、梅雨前線付近で大雨が頻発する時期で、なおかつ台風の影響が小さい6月では、集中豪雨事例に占める線状降水帯の割合は69%である[90]。特に、6月の停滞前線に伴う線状降水帯事例の割合は93%に達し、梅雨前線付近の集中豪雨のほとんどが線状降水帯によるものであることが統計的に示唆されている[90]。
より最近の気象研究所による過去事例の分析[注 5]によると、2009年から2023年までの15年間に日本では線状降水帯が計496回発生し、そのうち74.3%(369回)が夕方6時から翌朝9時までの夜間から早朝に発生していたことがわかった[91]。時期別では、梅雨期から台風シーズンの6月から9月にかけてが416回と全体の83.8%を占め、月別では7月が157回と最も多かった[91]。
線状降水帯による大雨の主な事例
強雨をもたらすバックビルディング型の線状降水帯は、特に梅雨期の九州地方で多いが、沖縄諸島から北海道まで、太平洋側と日本海側のいずれにおいても、線状降水帯が発生した事例がある[33]。以下に主な事例を示す。
Remove ads
観測・予測と予報
要約
視点
この節の加筆が望まれています。 |
発生条件の項で示した6つの条件は、線状降水帯そのものを予測するわけではなく、線状降水帯が発生しやすい幅広な領域を予測し、その発生の可能性を判断するためのものである[93]。したがって、当然のことながら予想の空振りは多数生じるが、線状降水帯による大雨発生の判断材料の一つとして、2016年(平成28年)5月30日から気象庁の予報現業で利用されている[93]。
顕著な大雨に関する情報

→詳細は「顕著な大雨に関する情報」を参照
気象庁は2021年(令和3年)6月17日より[94]、「大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で実際に降り続いている状況」下で、線状降水帯の発生を解説する[95]「顕著な大雨に関する情報」の提供を開始した[94]。運用には防災科学技術研究所が開発した線状降水帯自動検知システムを利用する[96]。
「顕著な大雨に関する情報」は、当該時刻、10分先、20分先、30分先のいずれかにおいて[95]、下記の4つの条件をすべて満たしたときに発表される[97]。
- 解析雨量(5kmメッシュ)において前3時間積算降水量が100mm以上の分布域の面積が500km2以上であること
- 1.の形状が線状(長軸・短軸比2.5以上)であること
- 1.の領域内の前3時間積算降水量最大値が150mm以上であること
- 1.の領域内の土砂キキクルにおいて土砂災害警戒情報の基準を超過、または洪水キキクルにおいて警報基準を大きく超過した基準を超過している(警戒レベル4相当以上である)こと
1.と2.は形状の基準、3.は雨量の基準、4.は危険度の基準を示している。現行のシステム上、これらの条件を満たせばバックビルディング型線状降水帯ではなくとも検知されてしまうという欠点はあるが、危険な大雨を捕捉できること自体が防災上重要であるため、十分に役立つ情報といえる。
2022年(令和4年)6月1日には、広域な地域(例:「九州北部」)を対象に、半日程度前からの予測情報(気象情報)の提供を開始し[98][99]、2023年(令和5年)5月25日からは、最大で30分先までの予測が発表されるようになり[100]、2024年(令和6年)5月27日には、発表区分が府県単位に細分化された[101]。しかし、府県単位での呼びかけについて、2024年度の実績では適中率・捕捉率ともに運用開始前の想定を下回っている状況にある[102]。
気象庁は中長期的な情報提供体制の改善について、線状降水帯による大雨の可能性を伝える事前情報として、2026年(令和8年)には2–3時間前を目標とした、より早い段階での予測情報の提供を開始するとし[103]、2029年(令和11年)までに市町村単位での危険度を危険度分布の形式で把握できるよう、半日前からの予測情報提供を目指すとしている[100]。
調査・研究
要約
視点
この節には複数の問題があります。 |
線状降水帯の構造やメカニズムに関しては、未だ解明されていない謎が多いものの[17]、さまざまなアプローチによる研究が試みられており、その理解が進んできている[26]。
日本の複数の研究機関は2019年から線状降水帯に関する発生機構解明研究や包括的観測プロジェクトを共同でスタートさせている[104]。主に九州や関東、西日本全域を研究フィールドとして選定し2023年まで行う。
具体的には下層や中層の水蒸気を観測する「水蒸気ライダー」「マイクロ波放射計」「地デジ波水蒸気観測」や雲の構造を3次元でスキャンする「MP-PAWR」、水滴の形状や湿度を計測する「ビデオゾンデ」、洋上GNSSを搭載した海上観測船といった最新の観測設備を西日本に配備し線状降水帯の雲システムと物理過程を捉える。またGPMやひまわり9号といった気象観測衛星から得られる水蒸気データも利用する。Metop-CやAquaに搭載されている「ハイパースペクトル赤外サウンダ」のデータを大気鉛直の水蒸気分布の把握に利用できないか検討する。航空機からのゾンデ投下も実施する。マイクロ波散乱計から得られる海上風データは数値モデルに取り込む。
また、得られた観測データと富岳による大規模シミュレーション実験を通して局地モデル(LFM)の計算式を改善させる[105]。具体的には雲物理過程の改良と積雲対流スキームの改良および高解像度化を実施する。現状でもMSMやLFMである程度線状降水帯が発生するかどうか診断することができるが、実際にどの場所で発生しどのぐらい停滞するか予測することは困難である。加えて人工知能や機械学習を利用した「発生確率、統合ガイダンス」の開発も行い、数値予報の高度化に繋げる。またデータの偏りがなく高精度な初期値の作成とモデル同化も予測の改善に繋がるため、手法を開発している[106]。
2023年3月より、気象庁は数値解析予報システムについて線状降水帯予測に特化したスーパーコンピューターを導入した[107]。
2023年8月には2029年の運用開始が目指されているひまわり10号について、既存の観測機能に加え大気の立体的な構造の観測が可能な赤外サウンダを導入し、線状降水帯を含む気象現象の予測精度の向上を図ることが提言された[108]。
民間気象会社のウェザーニューズは、線状降水帯が発生しやすい条件が揃ったかどうかを、面的に診断して可視化するソフトウェアを導入している[109]。またゲリラ雷雨解析の時代から培った「KN-Expert by LAPLACE」や超局地数値モデルなどを線状降水帯の発生予測に応用している。週間予報には海外や気象庁のモデルがそれぞれ得意とする現象をAIによって補正強化し、時刻的なブレを軽減するアンサンブル予報を取り入れている。
大気の川

グローバルスケールでみると、長さ数千キロメートル、幅数百キロメートルに及ぶ、地球の大規模な水蒸気輸送システムである「大気の川」とよばれる現象が、1990年代から観測されるようになっている[110]。「大気の川」は、熱帯から温帯低気圧に向かって多量の水蒸気を輸送する一帯で、湿舌に運ばれる水蒸気の「水源」となっている[111]。最近の例では、令和2年7月豪雨や令和3年8月の大雨で、その存在が認められている[110]。線状降水帯とも密接な関係があると考えられており、この大きな流れの中で発生しやすいとされている[110]。
発生報告が増えている原因

線状降水帯自体は昔から発生しているが線状降水帯、特にバックビルディング型の降水形態の発生報告が増えている要因としてはいくつか挙げられる。一つはアメダスや気象レーダーといった観測体制の充実によるものである。また統計解析ができるほどデータの分析手法が高度化したことも要因の一つである。
実際に線状降水帯そのものの発生頻度が増えているという統計解析は無いが、仮に増えている場合は地球温暖化による海面水温の上昇に伴う水蒸気の蒸発量の増加と気温上昇による飽和水蒸気量の増加(水蒸気フィードバック)が線状降水帯の発生を助けている要因の一つと考えられる。また、降水系の動きが遅く、停滞して災害をもたらすような現象が増加している場合も何らかの気候変化が影響していると考えられる。エアロゾルと呼ばれる大気汚染物質の微粒子の一つも関与が疑われている。
2023年度中にJAXAとESAは、エアロゾル分布と雲の内部構造までを透視して把握できる気象科学衛星を打ち上げる予定のほか、上述のように2029年までにはひまわり10号が打ち上げられる予定であり、太陽からの荷電粒子や宇宙放射線を観測できるセンサーも搭載される予定であるため雲の発生メカニズム解明により貢献できると期待される。
気温上昇と停滞性降水
線状降水帯の危険な特徴としては、その形状そのものよりも、同じ場所で積乱雲が湧き続けることが問題であるとされる。形状はあくまで積乱雲が流された結果として現れるものだからである。温暖化により下層の気温が上昇すると、その場所に含みうる水蒸気量の上限が引き上げられる。すると雨が降っても雲の材料供給がすぐには止まらず、長時間雲の発生条件が解消されにくくなる。
気候変動でよく言及される「降るはずのタイミングと場所で降らない」「雨が止むはずのタイミングで止まない」といった極端な現象の増加は大気中の飽和水蒸気量と関係していると考えられる。[要出典]
2022年12月27日に開かれた「線状降水帯予測精度向上ワーキンググループ」での報告[112]では、海面水温の前線によって下層大気の温度にも大きな変化が生じ、それにより大気下層の風の収束が強まり、積乱雲の発生に大きく影響している可能性が指摘された。
Remove ads
参考文献
- 荒生公雄、壺井美花「長崎半島付近で発生したライン状降雨―1997年7月11日の事例―」『天気』、日本気象学会、2000年、785–792頁、国立国会図書館書誌ID:5584818。
- 荒生公雄「長崎県南部地方における豪雨と地形」『長崎大学総合環境研究』環境科学部創立10周年記念特別号、長崎大学環境科学部、2007年8月、59–71頁、hdl:10069/21461。
- 大阪管区気象台ほか「強雨をもたらす線状降水帯の形成機構等の解明及び降水強度・移動速度の予測に関する研究」『気象研究所技術報告』第61号、気象研究所、2010年1月、doi:10.11483/mritechrepo.61。
- 加藤敦、三隅良平、平野洪賓、川田真也「2009年と2003年の福岡豪雨における浸水被害と降雨の時空間変動」『主要災害調査』第44号、防災科学技術研究所、2010年9月、11–20頁、doi:10.24732/nied.00001528。
- Kato, Teruyuki (2005). “Statistical Study of Band-Shaped Rainfall Systems, the Koshikijima and Nagasaki Lines, Observed around Kyushu Island, Japan” (英語). Journal of the Meteorological Society of Japan 83 (6): 943–957. doi:10.2151/jmsj.83.943.
- Kato, Teruyuki (2006). “Structure of the band-shaped precipitation system inducing the heavy rainfall observed over northern Kyushu, Japan on 29 June 1999” (英語). Journal of the Meteorological Society of Japan 84 (1): 129–153. doi:10.2151/jmsj.84.129.
- 加藤輝之「線状降水帯発生要因としての鉛直シアーと上空の湿度について」(PDF)『量的予報技術資料(平成26年度予報技術研修テキスト)』第20号、気象庁予報部、2015年2月、114–132頁、2025年10月10日閲覧。
- 加藤輝之「メソ気象の理解から大雨の予測について〜線状降水帯発生条件の再考察〜」(PDF)『量的予報技術資料(平成27年度予報技術研修テキスト)』第21号、気象庁予報部、2016年2月、42–60頁、2025年10月10日閲覧。
- 加藤輝之『図解説 中小規模気象学』(PDF)気象庁(監修)(改訂v2.1)、気象庁、2020年3月。2025年10月14日閲覧。
- Kato, Teruyuki (June 2020). “Quasi-stationary band-shaped precipitation systems, named “senjo-kousuitai”, causing localized heavy rainfall in Japan” (英語). Journal of the Meteorological Society of Japan 98 (3): 485–509. doi:10.2151/jmsj.2020-029.
- 加藤輝之「アメダス3時間積算降水量でみた集中豪雨事例発生頻度の過去45年間の経年変化」『天気』、日本気象学会、2022年6月、247–252頁、doi:10.24761/tenki.69.5_247。
- 加藤輝之『集中豪雨と線状降水帯』朝倉書店〈気象学ライブラリー3〉、2022年11月。ISBN 978-4-254-16943-0。
- 加藤輝之「集中豪雨をもたらす線状降水帯 ~基礎研究が生み出した防災用語~」(PDF)『第21回 都市水害に関するシンポジウム論文集』、土木学会、2022年11月、1–7頁、2025年10月4日閲覧。
- 加藤輝之 (2023年1月). “線状降水帯のレビューと今年度実施した集中観測の報告” (PDF). 気象研究所. 2025年10月14日閲覧。
- 加藤輝之「集中豪雨をもたらす線状降水帯について」(PDF)『消防防災の科学』第156号、消防防災科学センター、2024年5月、12–19頁、2025年10月4日閲覧。
- 金田幸恵、加藤輝之、吉崎正憲、坪木和久「長崎半島周辺における停滞性降水帯(諫早ライン)の構造と発達過程に関する研究②NHMを用いた数値実験」『大会講演予講集』第84巻、日本気象学会、2003年10月、185頁、NDLJP:10589260。
- 「顕著な大雨に関する気象情報について」(PDF)『令和3年度予報技術研修テキスト』、気象庁大気海洋部気象リスク対策課、2022年3月、1–36頁、2025年10月10日閲覧。
- 小林文明『線状降水帯 ゲリラ豪雨からJPCZまで豪雨豪雪の謎』成山堂書店〈極端気象シリーズ6〉、2023年8月。ISBN 978-4-425-51511-0。
- 小山芳太「奨励賞を受賞して―近畿地方に局地的大雨をもたらす降水システムの形成及び維持機構に関する解析的研究―」『天気』第62巻第2号、日本気象学会、2015年2月、143–144頁、NDLJP:10610426。
- 瀬古弘(著)、気象庁(編)「中緯度のメソβスケール線状降水系の形態と維持機構に関する研究」『気象庁研究時報』第62巻第1-3号、2010年、1–74頁、国立国会図書館書誌ID:10863194。
- 津口裕茂「新用語解説 線状降水帯」(PDF)『天気』第63巻第9号、日本気象学会、2016年9月、727–729頁、2025年10月4日閲覧。
- 津口裕茂、加藤輝之「集中豪雨事例の客観的な抽出とその特性・特徴に関する統計解析」『天気』第61巻第6号、日本気象学会、2014年6月、455–469頁、国立国会図書館書誌ID:025628271。
- “降水セルから見た甑島ラインの形成過程” (PDF). 名古屋大学気象学教室 (2003年8月). 2025年10月14日閲覧。
- 古川武彦、大木勇人『図解・気象学入門 原理からわかる雲・雨・気温・風・天気図』(改訂版)講談社〈ブルーバックス〉、2023年7月。ISBN 978-4-06-532633-6。
- 守田治「梅雨期の集中豪雨のメカニズム 第6回 都市水害に関するシンポジウム論文集」(PDF)、土木学会、2007年11月、2025年10月15日閲覧。
- 守田治「平成24年7月九州豪雨災害の気象特性」『Western Japan NDIC news』第48号、九州大学、2013年3月、3–9頁、NDLJP:11348822。
- 用貝敏郎「2003年7月20日、鹿児島県伊佐郡菱刈町で発生した豪雨の特徴」『大会講演予講集』第86号、日本気象学会、2004年10月、35頁、NDLJP:10589986。
- 横田寛伸「大阪の淀川チャネル型大雨におけるback building」『大会講演予講集』第63号、日本気象学会、1993年5月、6頁、NDLJP:10291263/1/19。
- Yoshizaki, Masanori; Kato, Teruyuki; Tanaka, Yoshinobu; Takayama, Hajime; Shoji, Yoshinori; Seko, Hiromu; Arao, Kimio; Manabe, Kazuo et al. (2000), “Analytical and numerical study of the 26 June 1998 orographic rainband observed in western Kyushu, Japan” (英語), Journal of the Meteorological Society of Japan 78 (6): 835–856, doi:10.2151/jmsj1965.78.6_835
Remove ads
脚注
関連項目
外部リンク
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads