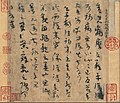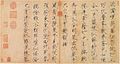トップQs
タイムライン
チャット
視点
中国の筆跡一覧
ウィキメディアの一覧記事 ウィキペディアから
Remove ads
中国の筆跡一覧(ちゅうごくのひっせきいちらん)では、有史以来、清代までの中国の筆跡の一覧を示す。時代ごとに名称・年代・筆者・書体・所蔵場所などを記す。
Remove ads
三代
殷
→詳細は「中国の書道史 § 殷(古文時代)」を参照
- 小臣艅犠尊(しょうしんよぎそん)
- 甲骨文
- 小臣艅犠尊銘
周
→詳細は「中国の書道史 § 周(古文・籀文時代)」、および「中国の書家一覧 § 周」を参照
- 大豊簋(たいほうき)
- 周代の最も早い時期の銅器。銘文は8行、78字であり、殷の甲骨文に似たところが多い[3]。
- 周公簋(しゅうこうき)
- 周代初期の銅器。銘文は8行、67字である[4]。
- 令簋(れいき)
- 大盂鼎(だいうてい)
- 大克鼎(だいこくてい)
- 毛公鼎(もうこうてい)
- 散氏盤(さんしばん)
- 虢季子白盤(かくきしはくばん)
Remove ads
秦
→詳細は「中国の書道史 § 秦(篆書時代)」、および「中国の書家一覧 § 秦」を参照
漢
前漢
→詳細は「中国の書道史 § 前漢」、および「中国の書家一覧 § 前漢」を参照
- 群臣上醻刻石(ぐんしんじょうしゅうこくせき、『趙二十二年刻石』とも)
- 魯孝王刻石(ろこうおうこくせき、『五鳳二年刻石』とも)
- 麃孝禹刻石(ひょうこううこくせき)
- 墓碑の先例と推測されている。円頭の長石に、「河平三年八月丁亥、平邑侯里麃孝禹」と2行に刻している[23]。
- 魯孝王刻石
新
→詳細は「中国の書道史 § 新」を参照
- 天鳳元年木牘(てんぽうがんねんもくとく)
- 萊子侯刻石(らいしこうこくせき)
- 萊子侯刻石
後漢
→詳細は「中国の書道史 § 後漢」、および「中国の書家一覧 § 後漢」を参照
- 開通褒斜道刻石(かいつうほうやどうこくせき)
- 石門頌(せきもんしょう)
- 礼器碑(れいきひ)
- 孔宙碑(こうちゅうひ)
- 封龍山頌(ほうりゅうざんしょう)
- 西嶽華山廟碑(せいがくかざんびょうひ)
- 『華山廟碑』ともいう。もと陝西省華陰県の西嶽山廟にあったものを、弘農郡の郡守である袁逢が旧碑に基づいて建てたものである。原碑はすでに失われて、拓本だけによって知られている。拓本の中でも最も著名なものは、「長垣本」・「関中本」・「四明本」の3種である。「長垣本」は、河南省長垣の王文蓀が所蔵していたが、欠損した文字は僅かに10字で、最もよく保存されている。昭和4年(1929年)8月、中村不折の所有となり、現在台東区立書道博物館に保存されている。「関中本」は、陝西省関中の東雲駒・雲雛兄弟の所有していたものである。「四明本」は、浙江省四明の豊熙が所蔵していたもので、両本とも100字余りの欠字がある。古来、蔡邕の書とか、郭香察の書とか言われているが、確証はない。漢隷として代表的なものの1つである。
- 史晨前碑(ししんぜんぴ)
- 全名は『魯相史晨祀孔子奏銘』(ろそうししんしこうしそうめい)という。2碑からなり、『史晨後碑』と合わせて『史晨碑』または『史晨前後碑』という。霊帝の時、魯国の相である史晨が孔子廟の祭典を盛んに行ったことを表彰したもので、山東省曲阜の孔子廟前に建てられている。碑文は、17行・各行36字で、字の大きさは3 cm、謹厳端正な隷書である。
- 史晨後碑(ししんこうひ)
- 全名は『魯相史晨饗孔子廟碑』(ろそうししんきょうこうしびょうひ)という。『史晨前碑』の裏に刻されていて、内容は、前碑建立の由来で、祭典が、官吏、孔子一門の弟子など、907人が参会して盛況であったことを述べている。また、更に孔子の旧跡を修繕して、諸施設を設置した官吏たちの功績を讃えている。碑文は、14行・1行36字である。
- 西狭頌(せいきょうしょう)
- 楊淮表記(ようわいひょうき)
- 魯峻碑(ろしゅんひ)
- 全名は『司隷校尉魯峻碑』(しれいこうい-)という。碑は、もと金郷山の魯氏の墓の側にあったが、のち任城県学から山東省済寧の州学に移された。碑高45.5 cm、幅136.4 cmで、碑文は17行・各行32字である。額には、「漢故司隷校尉忠恵父魯君子碑」と記されている。魯峻は、山陽昌邑の人で、桓帝の延熹7年(164年)司隷校尉となり、暴徒の粛正につとめて功績があったので、のちに屯騎校尉となり、霊帝の熹平元年(172年)に没した。碑は、その翌年、故吏・門生らによって建てられたものである。筆画は豊肥古雅である。なお建碑に関係した人たちの名を裏面に刻んであるが、その中に「妙」という字が草書体で書かれているのが珍しいとされている。
- 韓仁銘(かんじんめい)
- 熹平石経(きへいせっけい)→詳細は「熹平石経」を参照
- 白石神君碑(はくせきしんくんひ)
- 常山の相の馮巡、元氏令の王翊らが、白石神君の頌徳のために建てた碑である。碑文は16行・各行35字である。また、篆額は標題の5字で、碑文は八分を加味した方整な文字である。
- 張遷碑(ちょうせんひ)
- 全名は『蕩陰令張遷碑』(とういんのれい-)という。山東省穀城県の吏員らが、前任の県長で河南省蕩陰県令の現職にある張遷の徳政をたたえて建てた碑で、明代に発見された。碑は縦287.9 cm、横97 cm。篆額は双行で「漢故穀城長蕩陰令張君表頌」とあり、本文はその下に16行・各行42字ある。裏には発起人41名の姓名職名・醵金額が刻されている。本文には誤字異字がある(例えば「賓」を「殯」に、「氏」を「是」に、「曁」を「既と旦」の2字に分けたりしている)ので贋作説もあるが、書は方勁で古拙のため隷書入門として学ぶものが多くいる。
Remove ads
三国
→詳細は「中国の書道史 § 三国(隷楷過渡時代)」、および「中国の書家一覧 § 三国」を参照
- 公卿上尊号奏(こうきょうじょうそんごうそう)
- 受禅表(じゅぜんひょう)
- 葛府君碑(かっぷくんひ)
- 宣示表(せんじひょう)
- 薦季直表(せんきちょくひょう)
Remove ads
六朝
西晋
→詳細は「中国の書道史 § 西晋」、および「中国の書家一覧 § 西晋」を参照
- 皇帝三臨辟雍碑(こうていさんりんへきようひ)
- 月儀帖(げつぎじょう、『月儀章』とも)
東晋
→詳細は「中国の書道史 § 東晋」、および「中国の書家一覧 § 東晋」を参照
五胡十六国
→詳細は「中国の書道史 § 五胡十六国」を参照
南朝
→詳細は「中国の書道史 § 南朝」、および「中国の書家一覧 § 南朝」を参照
- 『瘞鶴銘』
北朝
→詳細は「中国の書道史 § 北朝」、および「中国の書家一覧 § 北朝」を参照
- 『鄭文公碑』(鄭羲下碑 碑額)
- 『元懐墓誌』(部分)
Remove ads
隋
→詳細は「中国の書道史 § 隋」、および「中国の書家一覧 § 隋」を参照
- 竜蔵寺碑(りゅうぞうじひ)
- 杜乾緒等造像記(とけんちょとうぞうぞうき)
- 美人董氏墓誌(びじんとうしぼし)
- 蘇孝慈墓誌(そこうじぼし)
Remove ads
唐
初唐
→詳細は「中国の書道史 § 初唐」、および「中国の書家一覧 § 初唐」を参照
- 『九成宮醴泉銘』(部分)欧陽詢書
- 『雁塔聖教序』(部分)褚遂良書
盛唐・中唐・晩唐
→詳細は「中国の書道史 § 盛唐・中唐・晩唐」、および「中国の書家一覧 § 盛唐・中唐・晩唐」を参照
Remove ads
五代・十国
→詳細は「中国の書道史 § 五代・十国」、および「中国の書家一覧 § 五代・十国」を参照
宋・遼・金
→詳細は「中国の書道史 § 宋・遼・金」、および「中国の書家一覧 § 宋・遼・金」を参照
元
→詳細は「中国の書道史 § 元」、および「中国の書家一覧 § 元」を参照
明
→詳細は「中国の書道史 § 明」、および「中国の書家一覧 § 明」を参照
Remove ads
清
→詳細は「中国の書道史 § 清」、および「中国の書家一覧 § 清」を参照
脚注
参考文献
関連項目
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads