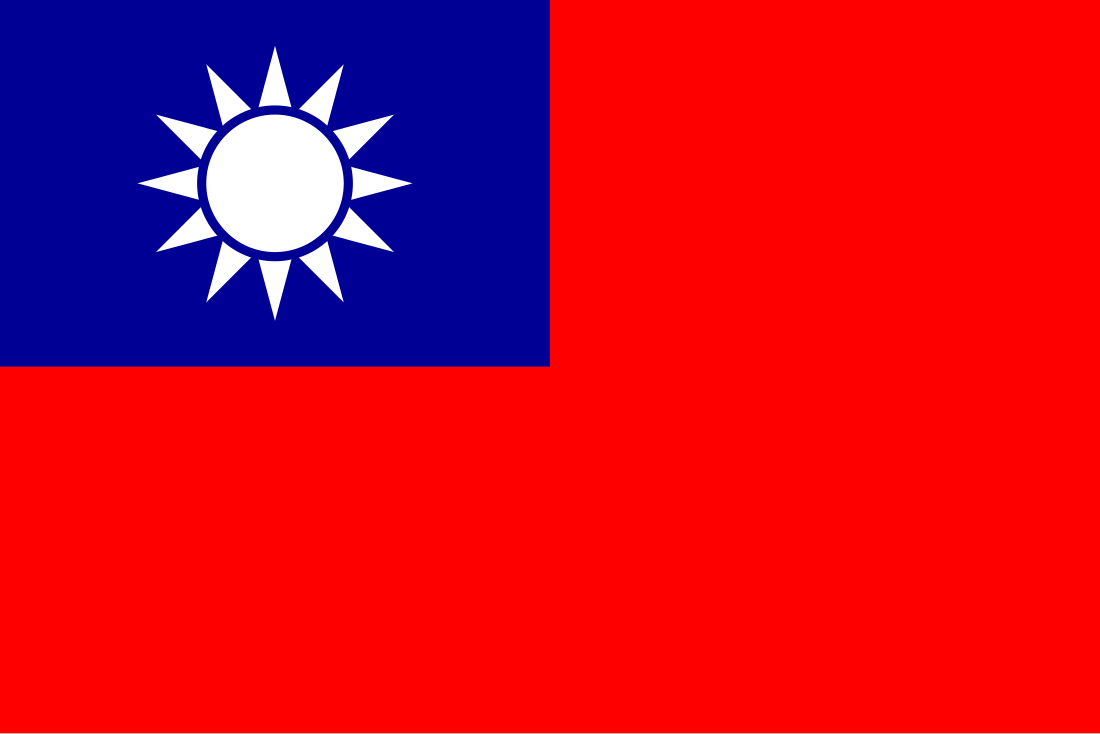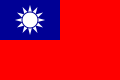トップQs
タイムライン
チャット
視点
中華民国海軍
中華民国(台湾)の海軍 ウィキペディアから
Remove ads
中華民国海軍(ちゅうかみんこくかいぐん、中華民國海軍、英語: Republic of China Navy)は、中華民国の海軍である。1911年の辛亥革命を受けての成立時点では清国海軍の後継組織だったが、国共内戦に敗れた中華民国は1949年〜1950年に中国大陸の支配権を一部の沿岸島嶼を除き喪失した。以降は、台湾の中華民国の海軍として存在しており、「台湾海軍」と呼称されることもある[1]。
Remove ads
現状
21世紀初頭の中華民国海軍の主な任務は、台湾本土や実効支配下にある離島からなる領土とシーレーンを、中国人民解放軍海軍による攻撃、侵入および封鎖から防衛することである。
なお、海軍が海上警察業務を兼ねたり海上警察組織を傘下に置いたりする国々は多いが、台湾では海上警察業務は海軍ではなく、日本の海上保安庁にあたる海巡署が独立して担当している。
作戦活動は台湾海峡および周辺海域の哨戒があり、これは戦時の反撃や対抗作戦と同様に重要視されている。中国による台湾を孤立させるための国際社会への圧力や外洋軍事進出に対応して、軍艦の自主開発・建造や台湾東部海域での作戦能力向上を図っている[1]。保有する艦艇の接頭語は ROCS (Republic of China Ship) となる。以前は CNS (Chinese Navy Ship) が使用された。
Remove ads
歴史
要約
視点
1911年 -(中国海軍)

国共内戦に敗れて遷台するまで、中華民国は中国大陸を統治し、海軍は中国沿岸海域や船舶の航行が可能な大河で活動していた。
中華民国建国後間もなく、清国海軍の装備と人員を引き継いだ中華民国政府は引き続き海軍を発展させるために海軍署を創設。1913年の第二革命では北洋政府の指揮下で革命勢力と交戦し、鎮圧に貢献した。 しかし1917年の護法運動(第三革命)において海軍総長の程璧光が麾下の第一艦隊を率いて孫文率いる広東政府に合流したため中華民国海軍は北洋政府の北洋海軍と広東の護法艦隊の二つに分裂した。 さらに経費不足、軍閥の割拠に加えて列強による武器禁輸政策によって、中華民国海軍の発展は停滞期に入る。その頃、中華民国は第一次世界大戦で戦勝国となり、海軍はドイツ帝国の河用砲艦を戦利艦として獲得した。
シベリア出兵中の1920年に起きた尼港事件では、アムール川を下った中国艦隊が、ニコラエフスクの日本軍兵営を砲撃する事件を起こしている[2]。この艦隊は1929年の中ソ紛争で痛手を受け、後に満洲国江防艦隊に編入する。
1928年の北伐勝利後に国民政府は海軍署を海軍部に昇格させた。軍務、艦政、軍械、海政、軍学、経理の六部が含まれ、さらに“十年建設”期間において、海軍は比較的大規模な建艦計画を立てた。初期の艦隊は艦船約44隻、総排水量3万tあまりだったが、日中戦争(支那事変)勃発直前には艦船58隻、5万tあまりまで増加していた。だが、日中戦争勃発後は経費節減のため、中央政府は海軍部を海軍総司令部に降格。日本軍の攻撃による損害は甚だしく、大型艦艇と沿岸部の領土のほぼ全てを喪失した海軍は僅かに残された砲艦で河川や湖に機雷を敷設し、日本軍が河川を利用して軍隊や補給物資が中国奥地まで運ぶのを阻止するだけだった。
1940年には汪兆銘が南京に対日融和的な政権を樹立し、重慶の蔣介石政権の海軍とは別に「中華民国海軍(和平建国軍海軍)」を設立した。しかしこの海軍は小規模なもので、また汪が自らの軍隊が戦争に加わるのを避け続けたため、目立った事績のないまま当人の死と日本の敗戦で消滅。民国海軍は蔣介石の下に統合された。
主な構成
国民党政権下では中華民国海軍は主に四つの海軍で成り立っていた。 日中戦争直前の状況は以下の通り[3]。
中央海軍(馬尾系)
- 第一艦隊
- 第二艦隊
- 砲艦 - 13隻:楚有、楚泰、楚同、楚謙、楚觀、江元、江貞、永綏、民生、民權、咸寧、德勝、威勝
- 河川砲艦 - 2隻:江鯤、江犀
- 水雷艇 - 4隻:湖鵬、湖鷹、湖鶚、湖隼
- 練習艦隊
- 巡防艦隊
- 測量隊
東北海軍(青島海軍学校系)
- 第三艦隊
- 海容級防護巡洋艦 - 1隻:海探
- その他砲艦など
広東海軍(黄埔系)
軍政部電雷学校(電雷系) ※軍事委員会直属
- 電雷学校快艇大隊
- イギリス製CMB魚雷快艇 - 8艘
- ドイツ製製Sボート魚雷艇 - 3艘
自国製軍艦は逸仙や砲艦などごく僅かで、ほとんどはイギリス製やドイツ製、日本製が混在していた。
有名な軍艦
1945年 -(国共内戦の当事者)
1945年、日中戦争の勝利により、中華民国は日本より賠償として数十隻の艦船を接収した。さらにアメリカ合衆国とイギリスからも艦艇の譲渡もしくは貸与を受けて海軍の再建を果たした。陣容は以下の通り[4]。
- 軽巡洋艦 - 1隻:重慶 ※旧・英『オーロラ』
- 駆逐艦 - 8隻:靈甫 ※旧・英『メンディップ』、丹陽 ※旧・日『雪風』、信陽 ※旧・日『初梅』、華陽 ※旧・日『蔦』、瀋陽 ※旧・日『波風』、汾陽 ※旧・日『宵月』、衡陽 ※旧・日『楓』、恵陽 ※旧・日『杉』
- 護衛駆逐艦 - 6隻:旧・米エヴァーツ級及びキャノン級
- 海防艦 - 17隻:旧・日『対馬』、『屋代』など
- LST揚陸艦 - 3隻
- LSM揚陸艦 - 10隻
- LCU揚陸艇 - 8隻
- その他砲艦・巡防艦多数:旧・米『ウェーク』、旧・イタリア『レパント』、旧・日『宇治』、『逸仙』、『永績』など
しかし国共内戦が再発し、戦況が共産側に有利になると、大量の海軍軍人が国民党政権に反旗を翻して主力艦の「重慶」や日本から接収した砲艦などの船ごと中国共産党へ投降した(重慶号事件及び第二艦隊叛乱事件)。その後、粛軍を行って態勢をなんとか立て直した(中華民国海軍白色恐怖事件)。 1949年の中華民国政府の台湾撤退に前後して、海軍艦隊は不利な状況下で舟山群島、海南島、大陳島など中国大陸沿岸の島々から撤退を行った。また艦隊は、北京の故宮の文物の台北疎開にも従事した。
台湾海峡の中国大陸側にある金門島、馬祖島、大陳列島と、南シナ海の東沙諸島と太平島は中華民国の実効支配下で保持されたものの、中華民国海軍の現実的な主任務は台湾(澎湖諸島など周辺島嶼を含む)の防衛となった。だがトルーマン政権のアメリカとの外交関係は冷え込んでおり、台湾もいずれ陥落する恐れがあった。
有名な軍艦
1950 -(事実上の台湾海軍)
1950年に朝鮮戦争が始まると、アメリカは極東政策を転換。一時は見捨てる(アチソンライン)かに見えた中華民国政府をアジア反共勢力の一員として支援する方向に切り替えた。アメリカは中華民国に第二次世界大戦時の軍艦を大量に供与。また第7艦隊を支援に充てて、中華人民共和国へ強い圧力をかけ続けた。
海軍を含む軍隊が大陸沿岸のわずかに残った島嶼を死守している間、蔣介石は大陸反攻の意思を捨てていなかった。関閉政策により中国大陸への海上封鎖を宣言。共産党支配下の港へ寄港しようとする第三国船籍の船舶を拿捕した他、大陸沿岸への襲撃作戦を実施した(東山島戦役など)。 蔣介石は中華民国海軍もいずれはアメリカの支援の下で(第二次世界大戦のノルマンディーや朝鮮戦争の仁川のような)中国本土上陸作戦を行うものと捉えていた。しかしソビエト連邦と中共が核兵器を保有すると、大陸反攻はキューバ危機のように連鎖的に世界を核戦争に突入させるリスクのある行為となり、アメリカはそのような状況を望まなくなった。米中全面衝突を望まないのは実のところ毛沢東も一緒だった。こうして(中ソ対立で毛沢東が海軍拡張を後回しにしなければならなくなったことも手伝って)、1960年代後半に入ると、1965年に発生した偶発的な東引海戦、東山海戦、烏坵海戦を除くと台湾海峡には暗黙の休戦状態が成立した。
1971年、中華民国は中国の国連代表権を失った。米中国交樹立に伴う対米断交もあって中華民国の地位は非常に不安定になった。中華民国は、蔣介石の跡を継いだ新総統蔣経国の下で、軍事戦略を攻勢主義から「攻守一体」に転換。1988年、李登輝に代替わりするまでの間に、大陸反攻の方針は段階的に放棄されていった。
この間、中華民国海軍は大型艦艇の国産ができず、防衛装備の供給をほぼアメリカに依存していた。しかし歴代のアメリカ政権は二つの中国政府との関係を常に気にする立場にあったので、提供される装備は常にその時点での米海軍の型落ち(ベンソン級、フレッチャー級、ノックス級、キッド級、ニューポート級)やダウングレード品(シコルスキー S-70ヘリコプター、シーチャパラルミサイル)だった。潜水艦の新規供与は拒否され続け、テンチ級が21世紀に入るまで運用されていた。中華民国海軍はフレッチャー級やギアリング級など第二次大戦型の駆逐艦も改装に改装を重ねて運用していた(武進改装)が、中華人民共和国が1980年代に改革開放で長い経済低迷から脱すると、中華民国も軍備旧式化の改善の必要性を認識。冷戦が終わり、第三次台湾海峡危機が起きると過度な対米依存のリスクも顕わになって、イスラエル製ガブリエル対艦ミサイルやフランス製ラ・ファイエット級フリゲート(康定級フリゲート)など、アメリカ以外の国の装備が海軍にも加わるようになった。
有名な軍艦
21世紀
2000年に成立した陳水扁政権は軍事戦略を「有効嚇阻・防衛固守」と定義付け、「制空・制海・地面防衛」「縦深打撃・早期警戒・情報優先」「境外決戦」の三つの柱を据えた。従って21世紀の中華民国海軍は大陸反攻ではなく、中国人民解放軍海軍による台湾封鎖への対処と着上陸侵攻の撃破を主任務としている。
台湾は四方を海に囲まれており、海軍の重要性は日に日に増している。したがって引き続きアメリカの退役艦の取得や艦隊の増強、並びに兵器の更新を行っている。また、老朽化が著しい潜水艦については[5]、2017年に自主建造(国産化)する方針が打ち出され[6]、2020年11月に最初の艦が着工した。8隻建造を目指している[7](海鯤級潜水艦)。さらに現有1隻だけの沱江級コルベットを2019年から順次、11隻量産する計画である。このように現在、海軍は国家の安全保障のために次世代の戦力増強を目指している。
Remove ads
組織

全般を統括する中華民国国防部海軍司令部の下、以下の主な部隊・機関がある。
現役装備
要約
視点
艦艇過去に就役した艦艇については「中華民国海軍艦艇一覧」「台湾海軍艦艇一覧」、『裝備の歴史』を参照。
潜水艦隊
駆逐艦隊
フリゲート艦隊
コルベット/哨戒艇艦隊
ミサイル艇隊
揚陸艦隊
機雷掃討/機雷敷設艦隊
補助艦隊
地対艦ミサイル
航空機
計画中/購買中
調達中(予算年度)
- 海昌計画:2500トン潜水艦(海鯤級)試作艦1隻[11][12][13](進水)(2019~2029年)
- 海鯤級潜水艦2-8号艦(2025-2038年)[14]
- 剣龍級潜水艦性能強化計画(2018年-2027年)[15]
- 承海計画:沱江級コルベット3-12号艦[16][17](2023~2026年、6隻就役、5隻建造中)
- 軽型巡防艦計画[18][19][20]:フリゲート試作艦2隻(2022年-2026年)(建造中)
- 康定級フリゲート性能強化計画[21][22][23](2022~2030年)
- 迅雷計画:ハープーン沿岸防衛システム(HCDS)[24][25]RGM-84L-4実弾ミサイル400発、RTM-84L-4訓練用ミサイル4発、ミサイル発射筒411個、地上発射型ハープーン発射車100台、レーダートトラック25台を含む。
- 永捷二号:FMLB-1級機雷敷設艇4-10号艇(2025~2027年)[26][27]
- 慧龍計画:2020年から5年間、無人潜水艦の原型を開発するために36億6,000万ドル以上の予算が確保され、2023年に原型を進水させ、さまざまなテストを開始することを視野に入れている[28](就役)[29]。
- 新型港内曳船[30]:(2020~2029年)円滑な港湾運営を維持するため、3,200馬力以上の港内曳船7隻を購入する計画で、投資額は9億6,802万元[31]。
- 新型浮ドック(2017~2027年)(建造中)[32]
- ファランクス近接防空システム[33]:新型ブロック1B新規購入13基、近代化改修ブロック1B8基(2017-2025)
- 威海計画:左営軍港拡張計画(2006~2032年)[34]
- 海軍陸戦隊FIM-92スティンガー携帯式防空ミサイルシステム[35](2017~2031年)
- 陸上型監視ドローン:これには48基の操縦装置と96架のドローンを含む(2023年-2028年)[36][37]。
- 艦載型監視ドローン:操縦装置8台、ドローン16機、飛行模擬機4機を含む(2023年-2028年)[36][37]。
計画中
- 戟海計画(元震海計画)[38][18][39][40]:新世代6500トンフリゲート試作艦(2026年予定)
- 潜水艦救難艦[41]:海軍は101億ドルを投じて潜水艦救難艦を建造する計画だ。
- 亢龍計画[42]:長距離大型誘導魚雷研究開発計画
- 鴻運2号計画[38]:玉山級ドック型揚陸艦2-4号艦建造計画
- 禛祥2号計画[38]:磐石級補給艦2号艦建造計画
- 神鷹3号計画:新規購入MH-60R統合多用途艦載ヘリコプター12機(2026年予定)[43]
- 大武級救難艦2-6号艦[44]
- 成功級フリゲート性能強化計画
- 新世代ミサイル駆逐艦建造計画[38]
- 迅能計画:新世代攻撃輸送艦建造計画[45]
- 震平計画:新世代強襲揚陸艦建造計画[38]
- 新型海洋測量艦建造計画[38]
- 海軍陸戦隊「105装輪戦闘車」60両[46](2024~2036年)
- 無人機雷処分具[47]
- 海軍陸戦隊攻擊型ドローン[48]
Remove ads
装備の歴史
要約
視点
種別並びに記号は『ミリタリーバランス』各号に依るため、公称類別と異なることに留意。
表中の「○」は配備情報のみで数量記載なし、「ε」は概数、「+」は記載数以上の保有を意味する。
潜水艦
水上戦闘艦
哨戒艦艇
機雷戦艦艇
両用戦艦艇
支援艦艇
無人機
固定翼機
回転翼機
地対艦ミサイル
Remove ads
階級
→「中華民国国軍の階級」も参照
士官
下士官及び兵
Remove ads
章
- 海軍の章
旗
- 軍艦旗
- 艦首旗
- 司令官旗
- 上級大将旗
- 大将旗
- 中将旗
- 少将旗
- 大佐旗
- 先任旗
- 戦隊長旗
- 長旗
- 当直旗
- 海道測量旗
脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads