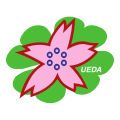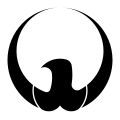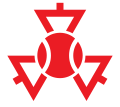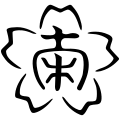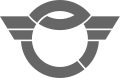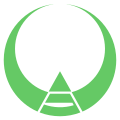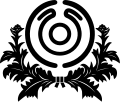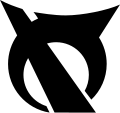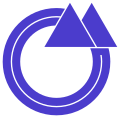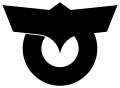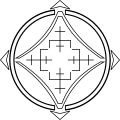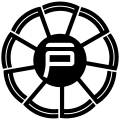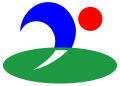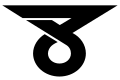| 市郡 | 町村 | 市町村章 | 由来 | 制定日 | 廃止日 | 備考 |
| 長野市 | |  | 「長」を図案化し、「の」を四つ組み合わせたもの[53] | 1907年5月[53] | 1915年10月 | 初代の市章である |
| 松本市 | | 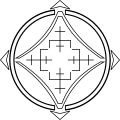 | 松葉を四つ表し、「本」を図案化したもの[54] | 1907年10月22日[54] | 1938年1月4日 | 初代の市章である |
| 長野市 | |  | 「長」を星の形に図案化し、「の」を表したもの[55] | 1915年10月[55][56] | 1966年10月16日 | 2代目の市章である |
| 篠ノ井市 | |  | 「しの」を二つの円(輪)を連鎖型(リンゴ型)として図案化したもの[57] | 1959年5月1日[57] | 篠ノ井町章(制定日不明[57])として制定されたものを市制施行後に継承された |
| 西筑摩郡 | 福島町 | 作成されていない | 1967年4月3日 | |
| 新開村 | 作成されていない | |
| 下水内郡 | 栄村 |  | 不明 | 1958年9月[58] | 1976年9月30日 | |
| 下伊那郡 | 鼎町 |  | 「鼎」を図案化したもの[59] | 1974年10月1日[60][59] | 1984年12月1日 | |
| 更級郡 | 上山田町 |  | 葛尾城主であった村上義清の紋章であったその紋章の「上の周りを丸で囲んだもの」を中心に配し、その周りに四つの「山」、更に周りに「田」で囲んだものであり、大正天皇の即位を記念して菊型に図案化したもの[61] | 1915年4月11日[61] | 1985年11月 | 上山田村章として制定され、町制施行後に初代の町章になる |
| 木曽郡 | 楢川村 |  | 全体はナラの実であり、三方向の突出したものは村内の三大字(奈良井・贄川・平沢)を表し、学校建設等各地区相互に利害関係を超越し、ナラの実の中に「楢」を配したもの | 不明 | 1989年7月18日 | 初代の村章である |
| 下伊那郡 | 上郷町 |  | 「上」を野底山を象徴する三角形で象り「郷」を小さめに浮かし、配したもの[62][63] | 1964年11月1日[64] | 1993年7月1日 | 上郷村章として制定され、町制施行後に継承される |
| 下伊那郡 | 上村 |  | 「上」を中心にし、シャクナゲの花と葉で囲んだもの[65] | 不明 | 1997年4月1日 | 初代の村章である |
| 更埴市 | |  | 「こ」と「し」を組み合わせて図案化したもの[66][67] | 1962年6月23日[66][67] | 2003年9月1日 | |
| 更級郡 | 上山田町 |  | 「カ」を図案化したもの[66] | 1985年11月[66] | 2代目の町章である |
| 埴科郡 | 戸倉町 | 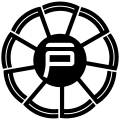 | 「戸」を中心にし、「ラ」を九つ付けている[68][66] | 1960年9月1日[66][68] | |
| 小県郡 | 東部町 |  | 「と」を図案化したもの[69] | 1962年4月2日[70] | 2004年4月1日 | |
| 北佐久郡 | 北御牧村 |  | 「北」を図案化したもの[71] | 1968年1月1日[70] | |
| 更級郡 | 大岡村 |  | 輪郭は「大」を形成し、その中央に「岡」を画いているもの[72][73] | 1915年11月5日[73][72] | 2005年1月1日 | 2代目の村章である |
| 上水内郡 | 豊野町 |  | 四つの「ト」が円を描ているもの[73] | 1955年1月1日[73][74] | |
| 戸隠村 |  | ソバの花を図案化し、中心部は「と」と小鳥を意味したもの[73] | 1967年11月1日[73][75] | 色は白色と緑色が指定されている[76] |
| 鬼無里村 |  | 「き」と一夜山・荒倉山・虫倉山とブナの原生林を円の中に図案化したもの[73][77] | 1971年11月3日[77][73] | |
| 木曽郡 | 山口村 |  | 「山口」を合体させ、簡明に図案化したもの[78] | 1975年11月1日[78] | 2005年2月13日 | 岐阜県中津川市と越境合併した |
| 南佐久郡 | 佐久町 |  | 千曲川を中心にして、全体は「さく」をあらわしたもの[79] | 1969年1月20日[79] | 2005年3月20日 | |
| 八千穂村 |  | 八ヶ岳山麓・千曲川と穂波の里を象徴し、「八千」を円形の中に図案化したもの[79] | 1976年1月[79] | |
| 東筑摩郡 | 四賀村 |  | 全体を円とし、「シガ」を組み合わせ、飛翔する鳥を形どったもの[80] | 1969年10月15日 | 2005年4月1日 | 1967年に制定されたものを[81]1969年10月15日に告示される[82] |
| 南安曇郡 | 奈川村 |  | 「な」を図案化したもの[83] | 1966年9月1日[84] | |
| 安曇村 |  | 「ア」を表し、中央の三山は乗鞍岳・穂高岳・槍ヶ岳などの山岳を示し、右下の部分は大正池・明神池・梓湖の水資源を表したもの[85] | 1975年4月7日[84] | 2代目の村章である |
| 梓川村 |  | 梓弓・梓川を形どったもの[86] | 1957年11月1日[84][86] | |
| 下水内郡 | 豊田村 |  | 四方に「ト」を配し豊を現しかつ「田」を外の囲いにして、中央に「十」を現し、「田」にしたもの[19] | 1957年4月[19] | |
| 木曽郡 | 楢川村 |  | 全体は「N」を図案化し、緑を想像する山々と青を想像する奈良井川を表し、悠久と清澄を意味したもの[87] | 1989年7月18日[88] | 色は緑色・青色・白色が指定されている[87]
2代目の村章である |
| 佐久市 | |  | 「さ」を鳥類の飛躍の姿に図案化したもの[89] | 1962年1月12日[89] | 初代の市章である |
| 南佐久郡 | 臼田町 |  | 「うす」を図案化したもの[90] | 1963年11月1日[90] | |
| 北佐久郡 | 浅科村 |  | 「ア」を図案化したもの[91] | 1966年12月13日[91] | |
| 望月町 |  | 「モチ」を左右対称に並べて図案化したもの[92] | 1960年10月10日[93] | |
| 下伊那郡 | 上村 | 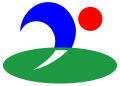 | 「上」を丸くして立体的に図案化して飛翔する村民の姿を表したもの[94] | 1997年4月1日[94] | 2005年10月1日 | 色は赤色・青色・緑色が指定されている
2代目の村章である |
| 南信濃村 |  | 「み」を図案化し、赤石山脈・伊那山地の山並みと伊那谷を力強く村に触れる様に表したもの[95] | 1975年[96] | |
| 南安曇郡 | 豊科町 |  | 「トヨ」を図案化したもの[97] | 1931年2月1日[97] | |
| 穂高町 |  | 「ホ」を円形に図案化したもの[97] | 1963年10月29日[97] | |
| 三郷村 |  | 「み」を図案化し、三つの円を表したもの[97] | 1966年3月30日[97] | 1966年3月17日に公表され、本年3月30日に制定された[97] |
| 堀金村 |  | 「ホリ」を円形に図案化したもの[97] | 1965年4月1日[97] | |
| 東筑摩郡 | 明科町 | 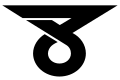 | 「ア」を意匠化したもの[97] | 1964年9月21日[97] | 1964年9月17日に公表され、本年9月21日に制定された |
| 小県郡 | 長門町 |  | 「ながと」を図案化したもの[98] | 1966年9月30日[98] | |
| 和田村 |  | 全田を丸としてかつ「わ」を図案化し、黒耀石の矢尻と山の表現に合せたもの[98] | 1975年2月1日[98] | |
| 上水内郡 | 牟礼村 |  | 「ムレ」を図案化したもの[99] | 1956年6月29日[99] | |
| 三水村 |  | 倉井用水・芋川用水・普光寺用水を図案化した[99] | 1988年2月22日[99] | 1926年12月26日から同年12月31日までに小学校の校章として制定されたものを[100]1988年2月22日に正式に村章として制定された[99]
当時の三水尋常高等小学校(現:飯綱町立三水第一小学校)教員の前島孝作の作品である[100] |
| 東筑摩郡 | 坂井村 |  | 「サ」・「S」を図案化したもの[101] | 1976年4月[102] | 2005年10月11日 | |
| 坂北村 |  | 「さ」を図案化したもの[103] | 1973年11月[102] | |
| 本城村 |  | 「ホン」を図案化したもの[104] | 1978年10月[102] | |
| 木曽郡 | 木曽福島町 |  | 「キソフ」を表したもの[105] | 1973年11月3日[106] | 2005年11月1日 | 1974年1月1日に再制定される[105][107] |
| 日義村 |  | 「ヒヨ」を組み合わせたもの[105] | 1976年10月1日[108][105] | |
| 開田村 |  | 「カイ」を表し、図案化したもの[105][109] | 1975年7月20日[105][110] | |
| 三岳村 |  | 「み」を羽ばたく鳥の形に図案化したもの[105] | 1972年5月1日[105][111] | |
| 北安曇郡 | 八坂村 |  | 「八」を簡易的に印象的に飛躍する二羽の鳥を想像し、表したもの[21] | 1973年11月28日[21] | 2006年1月1日 | |
| 美麻村 |  | 「ミアサ」を図案化したもの[21] | 1974年10月1日[21] | |
| 下伊那郡 | 浪合村 |  | 「ナミアイ」を図案化し、左側の弧が「ナ」・下部の重なる三角形が「ミ」・右側の弧が「ア」・中央上部が「イ」を表したもの[112][113] | 1978年6月25日[112] | |
| 上田市 | |  | 桜の花の真ん中に「上田」を図案化したもの[114] | 1950年11月1日[115] | 2006年3月6日 | 1919年5月1日に慣例として使用され、1950年11月1日に正式に制定された[115]
初代の市章である |
| 小県郡 | 丸子町 |  | 丸形の「子」を示したもの[115] | 1961年10月30日[115] | |
| 真田町 |  | 「サナ」を雁金に図案化したもの[115] | 1968年4月1日[115] | |
| 武石村 |  | 「武」を図案化したもの[115] | 1969年4月1日[115] | |
| 伊那市 | |  | 「イナ」を形造ったもの[116] | 1954年6月15日[117] | 2006年3月31日 | 1954年9月に再制定され、[118]更に1955年9月15日に再制定された[119]
初代の市章である |
| 上伊那郡 | 高遠町 |  | 「タ」を図案化したもの[120] | 1966年10月1日[118] | |
| 長谷村 |  | 「ハセ」を図案化したもの[121][122] | 1965年10月22日[121][118] | |
| 下伊那郡 | 清内路村 |  | 「セ」を円形に図案化し、飛躍する鳥を形成し、国道256号・黒川を表したもの[14] | 1969年2月11日[14] | 2009年3月31日 | |
| 上水内郡 | 信州新町 |  | 「しん」を円形に図案化し、中央の突起は部分は飛騨山脈(北アルプス)と町民の進取の気性を表しもの[123][3] | 1954年10月16日[3][123] | 2010年1月1日 | 新町章として制定され、信州新町改称後に継承された |
| 中条村 |  | 全体は虫倉山を表し、その中に「ナ」を図案化したもの[124][18] | 1968年11月3日[124][18] | |
| 東筑摩郡 | 波田町 |  | 「は」を図案化したもの[18] | 1973年4月1日[18] | 2010年3月31日 | |