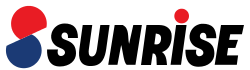トップQs
タイムライン
チャット
視点
サンライズ (アニメ制作ブランド)
日本のバンダイナムコフィルムワークスが使用するアニメ制作ブランド ウィキペディアから
Remove ads
サンライズ(英: SUNRISE)は、バンダイナムコフィルムワークスのアニメ制作ブランド。
かつてはバンダイナムコホールディングス傘下の株式会社サンライズ(英: SUNRISE INC.)という法人であった。同社は2022年4月1日に株式会社バンダイナムコフィルムワークスに商号変更し、同日以降サンライズの名称は同社のブランドとして継続している。
Remove ads
沿革
要約
視点
旧会社情報
創業
1972年、虫プロダクションから独立した有志により、アニメ制作会社株式会社創映社が設立される[2]。1972年9月、創映社の制作現場として有限会社サンライズスタジオが設立される[2]。
虫プロの制作・営業部門に所属していた岸本吉功、伊藤昌典、山浦栄二、渋江靖夫、岩崎正美、沼本清海、米山安彦の7名[注 1]が設立メンバーである。手持ちの資金がなかったことから、同年、虫プロ作品で音響を担当していた東北新社に出資を仰ぎ[3]、サンライズ創業者との共同出資により株式会社創映社を設立。創映社が企画と営業を行い、アニメの実制作はサンライズスタジオで行なう体制が取られた[4]。そのため、当初の営業・制作スタッフはサンライズスタジオと創映社に同時に在籍する状態であったが、創映社自体は東北新社の子会社で下請けの存在だったため、この当時に制作した作品の著作権表示は全て「©東北新社」となっている。
本社が設立された1972年は、彼らの独立元ともいえる虫プロ(旧虫プロ)や、その関連・子会社の経営難や労働争議が表面化しつつあった頃でもあった。これは企業の成り立ちや手塚の意向、および経営方針がゆえに「アニメーターにあらずんば人にあらず」と言われる程に、アニメーター偏重の作品作りが最優先される企業風土となったことで、合理的で適切な企業運営ができなかったことが主な要因となったものであった。
創業メンバーは、旧虫プロが倒産直前の末期的様相を呈する前に独立した面々ではあるものの、同社の内情と体質的な問題を組織内部から見て知る者たちでもあり、この企業体質がサンライズスタジオの経営における大きな教訓として、現在まで受け継がれている。すなわち、サンライズにおける「クリエーターが経営陣に入ってはいけない」という経営ポリシーの確立である[5]。そのため創業以来、自社スタジオは構える一方で、制作進行管理業務以外の実制作作業は外注スタッフがほぼ全てを担っており、既に50年近い歴史を持つ企業でありながら、サンライズ一筋のプロパー正社員として監督を務めた人物もいない[注 2]。これもまた、アニメ制作に必要なスタッフや、専門職の大半を自社で正規雇用として抱え続けたために、昇給・人件費増加・社内ポストなどの問題が解決できずに、労働争議に至って破綻した旧虫プロの反省でもあった。そのような意味において言えば、サンライズでヒット作を手掛けてその名を知られる富野由悠季・高橋良輔などの監督や、塩山紀生・安彦良和・木村貴宏などの著名アニメーターもあくまで外注スタッフに過ぎず、クリエイターは携わっても作品単位での企画・制作までにとどまっている。
また、創業当初の経営陣はアニメの作品性も重視する一方、それ以上に必要に応じた外注の多用などコスト削減や各種版権収入なども含めて、総合的な採算確保を図り健全経営を維持することを最重視する経営方針を打ち出した。玩具の商品企画のタイアップを、アニメ企画の起点と主軸に据える作品構築のシステムを採用していたことも、今日に至るサンライズを形成した重要な特徴の一つである[6]。この背景には「資金のない弱小プロダクション故に人件費を負担できない」[7]、漫画原作の著作権(翻案権)を得るために必要な予算が捻出できない、などといった経営初期に抱えていた資金面にまつわる事情がある。一方で出版物を原作とした作品の場合、アニメ雑誌が記事に取り上げる際、著作権者の意向という形で誌面の素材として使用したい映像の使用許諾が得られなかったり、ページ数の制限が付きまとうことが多く、サンライズ作品におけるオリジナル企画の多さは、1980年代を中心にアニメ雑誌においてメインに据えられ、大きく取り扱われる要因となった[8]。
日本サンライズ時代

1976年11月に東北新社傘下から離脱。株式会社日本サンライズ(英: NIPPON SUNRISE INC.)に改組・商号変更し、東映本社作品と円谷プロ作品のアニメーション制作を下請けするようになる。一説には、利益の配分を巡る喧嘩別れとも言われており[9]、サンライズの飯塚正夫によると、『ゼロテスター』や『勇者ライディーン』などで得た利益はすべて東北新社に行っており、彼らは給料が上がらず不満が溜まっていたという[10]。翌1977年の『無敵超人ザンボット3』にて初めて自社企画制作作品を世に送り出す。1979年制作の『機動戦士ガンダム』とその後の劇場用作品により、アニメ業界にリアルロボットブームを巻き起こした。
1981年、初代社長の岸本吉功が死去。当時まだ40代であったが、激務が祟り、健康を害した事による早逝だったという[11]。岸本の死を受け、第2代社長に伊藤昌典が就任。
1985年、オリジナルビデオアニメ(OVA)に進出。OVAという体裁こそ取っているものの、サンライズ制作のそれにおいて全くのオリジナル企画は少なく、『装甲騎兵ボトムズ』のようなテレビシリーズで人気を得た作品の続編や、『機甲猟兵メロウリンク』のようにその延長線上にある企画という基本方針を取っている。
株式会社サンライズ
1987年6月に株式会社サンライズへ商号変更し[2]、第3代社長に山浦栄二が就任する。この商号変更と山浦の社長就任に伴い、従来のオリジナル企画主体の路線から転換し、『ミスター味っ子』『シティーハンター』『バツ&テリー』などを端緒に、漫画原作付き作品を手がけることが増えていった。これらの作品では演出として著名な映画・ドラマ・アニメ[注 3]、制作当時の時事ネタなどのパロディを取り入れるようになり、以降同社制作アニメの特徴のひとつとなってゆく。
またこの頃は、『ガンダム』に端を発したリアルロボットブームが下火になりつつあった時期でもあり、その火付け役であったサンライズもまた同年放送の『機甲戦記ドラグナー』を最後に、リアルロボット系作品に依存した体制からも一旦脱却。玩具メーカーとのタイアップのオリジナル企画においても、『魔神英雄伝ワタル』を機に子供がロボットに乗る、もしくはロボットと友情を育むことで敵を倒すロボットアニメをてがけた他、『鎧伝サムライトルーパー』の関連作品の成功を受ける形で、容姿端麗な美少年が特殊アーマーを装着する、いわゆる鎧ものにも力が入れられた。
当時サンライズが入居していたビルでは、1階がスタジオ、2階が企画室とされ、本社は3 - 5階に置かれていた[12]。石垣純哉は、有名なロボットアニメを多数手がけるサンライズは上井草駅前に自社ビルを有する大企業だと思っていたが、実際に訪れると小さなビルで、Tシャツにジーンズというラフな姿の若者が出迎えたことに驚いたという[12]。
1990年代前半には、当時のガンダムよりも下の年齢層をメインターゲットとした『勇者シリーズ』が商業的な成功を収めるなど、元々得意とするオリジナル作品も堅調に推移した。
バンダイ(バンダイナムコ)グループ傘下企業へ
1994年4月1日、バンダイによる資本参加を受けて同社傘下のグループ企業となる。これに伴い経営陣も刷新され、以降の経営上層部の人材は松本悟のように、主にバンダイの送り込んだ人物が占める様になっていった。
川口克己によると、バンダイグループ内部には出資した作品のマーチャンダイジングの成功・不成功の判断基準として、『ガンダム』シリーズを指標に用いる向きがあり、同シリーズと同程度の売上でないと作品として成功とは見なされないことから、自然とガンダムに偏重していく傾向があるという[13]。サンライズ作品に限らず、「ロボットアニメはガンダムに淘汰される」という見方すらある[14]。このため勇者シリーズが終了した1990年代末以降はサンライズ自身でさえ、少年向け・低年齢層向けのロボット物のオリジナルアニメ作品を発表する機会にはなかなか恵まれなくなった。
またバンダイグループ(バンダイナムコグループ)は、版権・キャラクター関連のビジネスでは長年の業界最大手として豊富なノウハウを持っているが、その裏返しとして同社が関与する作品において、版権や制作体制全般の管理が極めて厳しく徹底されることでも知られている。サンライズもバンダイグループ入りの後はその例に漏れず、版権ビジネスだけではなく作品出演の声優や原作者・監督などのメディア出演についても、管理がより強化・徹底されるようになっていった。
以後の沿革・歴史は下記にて年代ごとに記載。
1990年代 - 2000年代

1994年、CG制作を中心とするサンライズデジタルクリエイションスタジオ(SUNRISE D.I.D.)を設立。以後、サンライズ作品内にてデジタル彩色やCG処理が導入された。導入初期の時期では3D寄りの表現は『勇者王ガオガイガー』及び『ダイノゾーン』が、デジタル彩色は『第08MS小隊』の映像特典である宇宙世紀余話や『天空のエスカフローネ』など一部の作品で採用されていたが、新作がすべて全編デジタル制作に移行するのは設立から9年後の2003年と他会社と比べて比較的遅い時期となった。
1996年10月、本社を東京都杉並区上井草2丁目35番11号から同区上井草2丁目44番10号へ移転。
2002年6月、全額出資子会社として、作品の音楽著作権を管理する音楽出版社「サンライズ音楽出版株式会社」を設立。
2005年10月からは株式会社バンダイ、株式会社ナムコとの経営統合に伴いバンダイナムコグループの一員となる[2]。ナムコ系テレビゲーム作品とのタイアップが増える。一例としては2007年に制作された、『THE IDOLM@STER』を原案とした『アイドルマスター XENOGLOSSIA』、2008年制作の『テイルズ オブ ジ アビス』のアニメ版などが挙げられる。それとは対照的に、かつての主軸でもあった玩具をメインとしたコンテンツとのタイアップ作品は、2004年の『陰陽大戦記』以降は激減した。ガンダム以外のオリジナルロボット作品についても、『コードギアス』シリーズや『ゼーガペイン』など、少数に留まる(一方で、この2作については初動から10年経過した2010年代でも適宜シリーズの展開が続いている)。
2010年代
2010年代には、自社参加・読者参加企画発祥のメディアミックス作品『ラブライブ!』が大ヒットを飛ばしたことを筆頭に、以前よりも更に様々なジャンルの作品を手がける様になった。
- ゲームを主軸とした企画とのタイアップ作品 - 『バトルスピリッツ』シリーズ、『アイカツ!』など
- コミック原作作品 - 『銀魂』『ケロロ軍曹』など
- 非コミック原作作品 - 『境界線上のホライゾン』・『アクセル・ワールド』(ライトノベル原作)など
2015年4月1日、キッズ・ファミリー向け作品などの一部の制作部門を分社した、株式会社バンダイナムコピクチャーズが設立される(事前発表は同年2月12日。以下「BNP」と略す場合あり)。社長はサンライズ社長の宮河恭夫が兼任する。これ以降のサンライズは、ハイターゲット向けの作品を中心とした制作体制に特化することとなる。
2016年9月、サンライズ内部で独自に立ち上げた、非映像系オリジナル作品(主に小説)を発信するwebサイト「矢立文庫」をスタート。
2018年、CGアニメ制作会社のサブリメイションと資本提携を締結[15]。同年11月20日、ジーベックのポストプロダクション部門を除く映像制作事業を譲受すると発表。その後同社の撮影部門、練馬スタジオ、仕上部門および過去作品の著作権を除くアニメーション作画・制作管理部門の譲受に変更された。これを受けて、2019年3月1日付で新会社「株式会社SUNRISE BEYOND」(サンライズビヨンド)を設立し、4月1日付で同社にこれらの事業が継承された[16][17][18][19]。
2019年4月1日、宮河恭夫のバンダイナムコエンターテインメント社長就任に伴い、専務取締役の浅沼誠が社長に就任[20]。同日、サンライズ音楽出版の社名を「株式会社サンライズミュージック」に変更する。
2020年代
2021年3月1日、半世紀近くに及ぶサンライズの過去作(BNPに移管したシリーズ作品、およびガンダムシリーズなど別途ポータルサイトのある作品以外が中心)と、その関連情報をエンタメ的にアーカイブするサイト「サンライズワールド」を開設。これと連動する形で、2014年にYouTubeに開設されていた「サンライズチャンネル」にて、『無敵超人ザンボット3』を始めとした1970 - 1990年代初めごろまでの過去作を対象とした、期間限定でのプレミア無料配信も行われるようになった[注 4]。
2021年10月、東京都杉並区荻窪4丁目30番16号藤澤ビル内に新本社を設立。オフィスの名称は『機動戦士ガンダム』に登場する戦艦から取って「ホワイトベース」と名付けられており、サンライズも含めたグループ4社(サンライズ・BNP・SUNRISE BEYOND・サンライズミュージック)と、都内に20ヶ所以上ある制作スタジオなどの拠点を、新本社に移転集約させることになっている[21][注 5]。
また、同19日にはバンダイナムコホールディングスの取締役会において、2022年4月にバンダイナムコグループのIPプロデュースユニットに属する企業の再編が実施されることが決定し、2022年2月8日には再編に伴う商号の変更も発表された[23]。これに伴い、サンライズはバンダイナムコアーツの映像事業とバンダイナムコライツマーケティングを統合した、グループ全体で映像事業を担う新会社「株式会社バンダイナムコフィルムワークス」(以下BNFW)に、子会社のサンライズミュージックはバンダイナムコアーツを存続会社として、バンダイナムコライツクリエイティブとともに統合される音楽・ライブイベント事業を担う新会社「バンダイナムコミュージックライブ」(以下BNML)にそれぞれ移行[24]。再編により「サンライズ」の名称は法人としては用いられなくなるものの、BNFWの商標・ブランド名としては今後も引き続き使用される[23]。
Remove ads
制作作品
要約
視点
サンライズで制作されている作品は、全部で12箇所のスタジオが母体となっている[注 6]。2015年4月にバンダイナムコピクチャーズが設立されて以降は、これらのスタジオの一部は同社に移管されている。
以下、☆印の付記されたものは、バンダイナムコピクチャーズ設立時に同社に移管された作品・シリーズを指す。
テレビアニメ
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
単発テレビスペシャル
劇場アニメ
1980年代(劇場)
1990年代(劇場)
2000年代(劇場)
2010年代(劇場)
2020年代(劇場)
OVA
※テレビシリーズの総集編はほぼ除外
1980年代(OVA)
1990年代(OVA)
2000年代(OVA)
2010年代(OVA)
2020年代(OVA)
Webアニメ
ゲーム
制作協力
その他
Remove ads
歴代代表取締役社長
ラジオ番組
- サンライズラヂオBREEZE - 東海ラジオで放送。北海道・九州へもネットされ、ランティスウェブラジオでも配信されていた。
関連人物
演出家
- 青木康直
- 秋田谷典昭
- アミノテツロー
- 阿宮正和
- 井内秀治
- 五十嵐達也
- 池田成
- 池野昭二
- イシグロキョウヘイ
- 井上ジェット
- 今川泰宏
- 今西隆志
- 岩井国治
- 鵜飼ゆうき
- 江上潔
- 大橋誉志光
- 岡本英樹
- 小倉宏文
- 小原正和
- 鹿島典夫
- 加瀬充子
- 片山一良
- 川瀬敏文
- 神田武幸
- 喜多幡徹
- 京極尚彦
- 工藤寛顕
- 河本昇悟
- 北村真咲
- 近藤信宏
- さとうけいいち
- 佐藤照雄
- 下田久人
- 下田正美
- 杉島邦久
- 高木茂樹
- 高田耕一
- 高橋良輔
- 高松信司
- 高山功
- 滝沢敏文
- 宅野誠起
- 谷口悟朗
- 徳本善信
- 富野由悠季
- 長井龍雪
- 長崎健司
- 長浜忠夫
- 西山明樹彦
- 馬場誠
- 菱川直樹
- 菱田正和
- 日高政光
- 福田己津央
- 藤田陽一
- 藤原良二
- 古田丈司
- 町谷俊輔
- 松尾衡
- 松園公
- 松村亜澄(磨積良亜澄)
- 水島精二
- みなみやすひろ
- 三好正人
- 三宅和男
- 向井正浩
- 村田和也
- 元永慶太郎
- 森邦宏
- 谷田部勝義
- 吉村章
- 四辻たかお
- 米田和博
- 米たにヨシトモ
- 綿田慎也
- 渡辺信一郎
- わたなべぢゅんいち
- 渡邊哲哉
アニメーター
キャラクターデザイナー
キャラクター作画監督
メカ作画監督
その他のアニメーター
メカニックデザイナー
脚本家・小説家
制作・企画
その他
Remove ads
関連項目
サンライズ関連
バンダイナムコグループ
- バンダイナムコピクチャーズ
- アクタス
- エイトビット
- SUNRISE BEYOND
- バンダイビジュアル - バンダイナムコフィルムワークス(旧:バンダイナムコアーツ)の映像レーベル。
- バンダイナムコミュージックライブ(ランティス)
- サンライズインタラクティブ
- 創通
- BANDAI SPIRITS(旧:バンダイ模型→バンダイホビー事業部)- ガンダムシリーズ(ガンプラ)及び同社制作のロボットアニメ作品(ザブングル、ダンバイン、エルガイム、バイファム、レイズナー等)のプラモデルを販売。
同社スタッフ・OBが独立・起業・移籍した会社
現在
- スタジオディーン - 仕上検査を務めた長谷川洋、もちだたけしが1975年に設立。
- スタジオダブ - 作画スタッフを務めた八幡正が1983年に設立。2019年に経営権を譲渡しBNPいわきスタジオとった。
- スタジオたくらんけ - 制作を務めた近藤康彦、山田浩之が1987年に設立。
- スタジオガゼル - プロデューサーを務めた佐藤郁夫が設立。
- ボンズ - 第2スタジオ出身でプロデューサーを務めた南雅彦らが1998年に設立。
- A-1 Pictures - アニプレックスの子会社として2005年に設立。プロデューサーを務めた植田益朗が同社を経て設立に参画[249]。
- ブリッジ - 第6スタジオ出身でプロデューサーを務めた大橋千恵雄が2007年に設立[250]。
- おっどあいくりえいてぃぶ - プロデューサーを務めた古里尚丈が2011年に設立。
- 天狗 - 出身の福士直也がぴえろを経て2013年に設立。
- 武右ェ門 - 練馬スタジオのCGスタッフを務めた髙山清彦らが2014年に設立[251]。
- Creadom8 - プロデューサーを務めた尾崎雅之がバンダイナムコピクチャーズを経て2024年に設立[252]。
過去
関連企業・施設
- 中村プロダクション
- 上井草駅 - ガンダムモニュメント製作協力。かつての会社最寄駅。
- 荻窪駅 - 会社最寄駅。
- クローバー - 名古屋テレビ・サンライズ制作枠のロボットアニメ(「ザンボット3」から「ダンバイン」の途中まで)のスポンサー。1983年倒産。
- アオシマ - ザンボット3、ダイターン3、イデオン、トライダーG7、ダイオージャ等のプラモデルを販売した会社。
- シーエムズコーポレーション
- Wish - 日本サンライズの仕上げ部門が1987年の組織改変に伴い独立し発足した有限会社エムアイを前身としている。
- 旭プロダクション
- アニメフィルム
- デザインオフィス・メカマン
- ビックウエスト
- 円谷プロダクション
- ADKエモーションズ
- ビクターエンタテインメント
- 読売広告社
Remove ads
脚注
外部リンク
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads